19日(金) 終業式 終業式、児童代表の言葉。 2年1組全員が前に出て、言葉をいった。 イメージとしては、卒業式の呼びかけに近い。 転校する子のために、みんなで手紙を書く。 大掃除。 1学期の授業終了。 |
||||
18日(木) 合同授業 2組も、かなり軌道に乗ってきた。 今日は、一人ずつ音読させる。 空き時間に授業を参観。 1学期のまとめ。 明日は終業式。 児童代表の言葉は、2年1組が割り当てられている。 代表の子を選ぼうとしたが… 「やりたい」という子がたくさんいたので、予定を変更する。 代表は一人から、全員。 つまり、ひとり一言いわせるようにした。 さっそく、「代表の言葉」の作成にかかる。 |
||||
17日(水) 今日集会があることをすっかり忘れていた集会委員。 「先生、忘れちゃった…」 本当は、イントロ当てクイズをやる予定だった。 仕方がない。 私たちも、成績表に追われてチェックしなかったのだから。 イントロ当てクイズの変わりをさがす。 ああ、これがいい。 すぐに決まった。 2年生による音読である。 全文は練習していないが、なんとかなるだろう。 「今日、集会で音読の発表をします」 『スイミー』、『ふきのとう』を発表。 いきなりいわれても、それなりにできる。 実力がついてきた証拠。 きれいな声で、音読した。 避難訓練 集団下校。 ものすごい暑さだった。 |
||||
| 16日(火) あゆみ提出。 |
||||
15日(月) 全校朝会、台風の影響で強風。 コンディションが悪いときは、実力差がもろに出る。 育ってきた子は、微動だにしない。 合同授業 休み明けにしてはよかった。 残り1週間、10マス計算をパワーアップさせる。 ・漢字探し 新しい見つけ方を教える。 反対語 ・辞書引き ・音読『スイミー』 音楽の授業 10マス計算のテスト。 それぞれ、課題を決める。 『3けたの引き算』 作文 |
||||
12日(金) チャレンジタイム、1校時 合同授業。 今日は、昨日に比べると暑くない。 ※といっても30度はこえている… パワーアップをはかる。 フラッシュカード、声を出させる。 九九は、5の段、3の段が中心。 10マス計算、作戦タイムのときに個別指導。 一人ひとりに声をかけていく。 とくに、まだ力を発揮できていない子。 +2がクリアできない子には、かなり指導を入れる。 結果やいかに? 今日は、はじめて10秒切ることができた。 これが、成長のきっかけになるだろう。 昨日までとはうってかわっての笑顔。 漢字探し 昨日教えた字を書くようにいう。 板書、雨、雲、曇り、電、雷、霜 筆写 今日は、なにぬねの 運筆を教える。 45度の打ち込み、力を入れるところ、すっと書くところ、リズム 辞書引き 「い」のつく言葉 『ぞうさん』の授業
いろいろな読み方で。 ・遠くにいるぞうさんに ・はなれているぞうさんに ・近くのぞうさんに ・うんと近くのぞうさんに その他いろいろ。 音読『スイミー』
|
||||
11日(木) |
||||
10日(水) |
||||
9日(火) チャレンジタイム、1年1組の授業を見せていただく。 ・フラッシュカード たして7になる数、たして10になる数 ・計算練習 1校時の10分間、1年2組の授業を見せていただく。 音読の授業が中心。 |
||||
8日(月) 夏の暑さにも負けぬ… 東京は、猛暑。 梅雨明けを思わせる快晴。 朝から30度以上あった。 厳しい中で、全校朝会。 教室に戻っても、あちーっ。 「暑いといえば、もっと暑くなります」(教師) といっている本人が、心の中で「あっちー」 汗だくで授業をした。 教師も子どもも。 校内研、低学年部会の公開授業がスタート。 今日は、私の番である。 9:00〜9:10、10分間授業を見ていただく。 1 フラッシュカード 2 10マス計算(+算、−算、×算) 3 音読『ふきのとう』の一斉表現読み 明日は、1年生の授業を見せていただく。 算数の授業 1学期の総復習 できが悪かったのが「10を29集めた数」である。 わかれば簡単なのだが… わからない子には、難しい。 コツを教える(秘) 『たんぽぽ』の作文。 10マス計算のテスト 休み明け、そして猛暑を吹っ飛ばす躍進ぶりにびっくり。 あゆみ(通知表)作成にかかる。 |
||||
5日(金) おーっ、やったな! 合同授業、かなりよくなってきている。 やる氣のない子が、変わってきた。 「先生、2の段切れるようになったよ」 「おーっ、やったな!」 このような会話が多い。 いいことだ。 七夕の飾りつけ 『たんぽぽ』の作文 水泳指導 2回目 1年生は、怖がる子1人のみ。 後の子は、大丈夫。 すごい。 2年生は、3人。 そのうち一人は、もう浮けるようになった。 水慣れのための遊び、各種。 蹴伸び 子どもたちのよる授業 生活科→総合的な学習を見据えて 自分たちで授業をさせる。 教師は、見ている。口出ししない。 「黒い目のきれいな女の子」の2回目。
今日は「黒い目の」で点を打つ。 「黒い目」、「きれい」についての検討である。 たくさん意見が出された。 |
||||
4日(木) コツを知り努力する 合同授業 新しいことを入れていく。 10マス計算、引き算。 まずは、ー10 10から一桁の数を引く。 1回目、10秒でできた子は少なかった。 多くの子は、できない。 ここで、コツを教える。 「引き算は、たし算」 「組み合わせを覚えよう」 説明する。 「10引く2は、8ですね」 「2に何をたせば10になりますか」 「8」 「そうですね。では、5では?」 「5」 組み合わせを覚えさせる。 「8と2,2と8」 「たし算は、逆にしても答えは同じなんですね」 ・0と10 ・1と9、9と1 ・2と8、8と2 ・3と7、7と3 ・4と6、6と4 ・5と5 2回目、やらせる。 10秒切った子が半数。 びっくりするほど増えた。 「できた!」 の大合唱。 3回目、さらに合格者は増えた。 コツを知って努力することが大切であることを教える。 七夕に向けての取り組み 願いごとを書かせる。 ・家族について ・自分について 「ゲームボーイがほしい」この手のものは、却下する。 ※一人だけ。昨日休んだ子。 後の子の意識は、さすが。 上のようなことを書いた子はいなかった。 裏に、実現のために何をするかを書かせた。 具体的に。 「黒い目のきれいな女の子」の授業 七夕とのリンク授業 見方・考え方を教える。 Mさんのセンスは、抜群。 すばらしい意見を連発した。 たとえば… 「黒いというのは、何が黒いのですか」 「顔が黒いのですか、全部が黒いのですか」 などなど、私も真っ青な発問。 代わりに授業をやってもらおう(笑) |
||||
3日(水) すばらしい! 音楽朝会 『翼をください』 地声を許してしまうと… 合同授業 音楽朝会後、体育館に残って授業。 音楽の先生にお願いして、伴奏していただく。 『翼をください』 続けて、音読。 これがよかった。 ※聴きたい人は、新河岸小にきてください。 すごくおもしろいです。 響き、声の美しさ… すばらしい(ほめすぎか?) 初めての水泳指導 |
||||
| 2日(火) 合同授業 文章題、『長さ』 2年生の漢字指導 いろいろな漢字を教える。 『たんぽぽ』の作文。 その他いろいろ。 |
||||
| 7月1日(月) 予定変更 7月に入る。 本来なら、先週から一氣にスパートするはずだったが… 諸事情あり、大幅な予定変更。 月曜は、リハビリ。 合同授業 文章題の授業 生活科 『たんぽぽ』 トップの子は、40枚を越えた。 その他いろいろな授業 ワークテスト(算数) 予想通りの結果(笑) 寸分の狂いなし。 歌『翼をください』、『語りかけよう』、『いつも何度でも』 |
||||
28日(金) 加速度的成長 合同授業 ※都の指導主事参観 だんだん軌道に乗ってきている。 ・フラッシュカード ・九九 2の段と5の段 ・10マス計算…たし算とかけ算 ・漢字探し ・筆写 あいうえお ・辞書引き ※今日から ・音読『ふきのとう』と『スイミー』 筆写は、「あいうえお」を書かせる。 1分間で何文字書けるか。 数え方は、「あいうえお」で1セット。 たとえば、「あいうえお あいうえお あいうえお」だったら、5×3=15 と数える。 半端な場合は、5×3=15 15+2=17 というように数えさせる。 ここでも、5の段の九九を使わせる。 音読 メインは、『スイミー』第2場面 「ある日、おそろしいまぐろが」の表現読み。 私が3つの読み方を例示する。 ・恐ろしそうに ・恐怖にすくんで ・悲しそうに 全員で読む。 次に、読みたい子に読ませる。 これがおもしろかった。 2校時 文章題2題 写すのに時間がかかる子3人。 恐ろしいほどに時間がかかる(笑) 今日は、注意をする。 そして、指導。 『たんぽぽ』の作文。 大大大ブレイク! ものすごい! 「先生、もっとやりたい!」 「すごーく、おもしろい」 なにしろ、休み時間も半数の子が書いている。 20分休みも昼休みも… 「休み時間なんだから遊んだら?」 「いいの。作文のほうがおもしろいの」 という感じである。 Mさんは、4日間で30枚書いた。 1日目は、オリエンテーション。 実質3日間である。 1日10枚。 杉渕学級らしくなってきた。 続く子は、19枚。 18枚、17枚、16枚と続いている。 今までていねいにていねいに指導してきた。 それが一氣に花開いたという感じである。 各駅停車から新幹線! 驚くべき成長である。 「もう、それくらいでいいんじゃないの?」 「いえ、もっと書くの」 「やめられない、止まらない」というかっばえびせん状態が続いている。 いやはやすさまじい。 これぞ「生きる力」。 体育 水泳は低温のため中止。 合同体育。 ・ドリブル 見た人は驚く。あまりのうまさに。 NBAの選手のようなボールさばき(笑) これホント。 ・ドッジボールの練習 的当て ボールの投げ方を指導する。 アドバイスを素直に聴いた子は、めきめき上達。 女の子でも、速いボールを投げる。 ・スナップを使う。 ・身体をひねる。 特に前者を指導する。 的に当たる音が、がらっと変わった。 ・ボールキャッチ 前まわりしてボールをキャッチする。 しかし…前まわりができていない。 予定を変更し、前まわりの練習。 道徳&学級活動 「自分の力を自分で伸ばす」 10マス計算テスト こちらも、100点が半数を超えた。 90点2人、80点3人。 進境著しい。 作文、10マス計算、その他いろいろ 今、加速度的に成長している子どもたち。 6月前半とは別人である。 5倍、いや、10倍はよくなっている。 歌も、急にうまくなった。 |
||||
27日(木) やればやるほど 合同授業 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算…たし算 ・漢字探し ・音読 「先生、音読っておもしろいね」 「すごく楽しい」 辞書引き「ふ」のつく言葉 文章題 生活科&国語 『たんぽぽ』の作文。 枚数トップの子は、19枚。 休み時間も書いている。 「勉強が遊び」になっている。 九九の秘密 現在、6の段を練習している。 今後について話す。 7の段…7×7、7×8、7×9 を覚えればいい 8の段…8×8、8×9 9の段…9×9 「えっ、9の段って1個覚えればいいの?」 その通り。 あとは、やっているのである。 たとえば、9×3=27 これは3×9のときにやっている。 2年生の漢字指導。 |
||||
26日(水) どうしておもしろいの? 体育朝会 合同授業 ・フラッシュカード ・九九 5の段 ・10マス計算 テスト→実態把握→指導 ※+2が10秒切れない子、指を使っている子… これから指導しなくては。 ・漢字探し 3つのコースにわける。 ・自力でやる ・教師にヒントをもらう ・教師が書いたものを写す ・音読 昨日に比べ、ぐんとうまくなった。 辞書引き 「ひ」のつく言葉 筆写 漢字 「目」のつく漢字探し 体育 水泳、雨のため中止。 ・ドリブル ・シュート ものすごくうまくなった。 ・投げる練習。 女子を中心に教える。 ポイントは、スナップ。 『たんぽぽ』の作文、大ブレイク。 書き方のポイントをつかんだ子は、どんどん書いている。 「おもしろい」 「先生、国語嫌いだったけど好きになった」 「作文っておもしろいね」 「どうしておもしろいの?」 「すらすら書けるもん」 「考えがどんどん出てくるから」 「算数みたいにすらすらできる(すらすら書ける)から」 などなど。 |
||||
25日(火) 合同授業スタート 今日から、合同授業開始。 2年生は、遭わせて57人。 図書室でおこなう。 ・フラッシュカード ・10マス計算 ・漢字探し ・音読 である。 2校時 ・辞書引き 5校時 生活科 『たんぽぽ』のまとめに入る。 帰りに、10マス計算のテスト。 |
||||
| 24日(月) パワーアップ 全校朝会 特定の子が目立つ。 それ以外は、しっかり立てるようになってきている。 ・フラッシュカード 子どもたちにやらせる。 ・九九 6の段に入る。 覚えるのは、6×6、6×7、6×8、6×9の4つである。 ・10マス計算 パワーアップ! まずは、かけ算。 ×0、×1、×2、×5、×3、×4、×6まで。 一列10点(10秒切ったら)。50点取ったら合格。 その後、自分の弱点を練習させる。 裏面は、連続技。 ×0、×1、×2、×5、×3を50秒制限でおこなう。 たし算。 表面は、テスト。 一列10点。ぜんぶできると100点。 合格ラインは、70点である。 不合格の子は、個別指導。 裏面は、連続技。 100〜80点の子は、表面の問題を連続してやらせる。 70点以下の子は、+0、+1、+2、+9、+3まで、50秒制限でやらせる。 ・漢字探し トップの子は、5分で150個。しかも、驚くほどきれいな字。 すごいとしかいいようがない。 2校時 音楽 空き時間を使って、教室掃除。 3校時 国語 ・辞書引き 「は」のつく言葉 ・筆写力 「かきくけこ」 1分間で何字書けるか。 ていねいに速く。 運筆に氣をつけて→打ち込み、「すーっ」、リズム ・2年生の漢字指導 4校時 算数 文章題 さっとできる子が、増えてきた。 できない子全員が、私の指示を守っていない。 給食 おみやげを配る。 大喜びしていた。 5校時 生活科 花壇の手入れ、植物を見て氣づいたこと クラブ 花、花瓶などを買ってくる。 |
||||
| 21日(金) 自習 三方小研修会参加のため、子どもたちは自習。 |
||||
20日(木) 三方小へ チャレンジタイム 朝の読書 1校時 算数&国語 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ・漢字探し ・1年生の漢字 書き順と運筆 ・音読『たんぽぽのちえ』 2校時 算数&国語 ・辞書引き「ね」のつく言葉。 ・文章題 ひねった問題。 できない子は、教師の指示通りにやらない子。 3校時 音楽 4校時 国語 『たんぽぽのちえ』 5校時 子どもによる授業 三方小へ、出発 |
||||
19日(水) 客観視 児童集会 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ・漢字探し ・筆写「あいうえお」 ビデオ撮り 自分たちの音読、歌を客観視する。 文章題 辞書引き 「ぬ」のつく言葉 『たんぽぽ』の作文。 体育 基本の運動 ・ボールキャッチ ・投げ方 速く強いボールの投げ方 校内研 長瀬さんの授業 |
||||
18日(火) ていねいに速く wカップ、日本惜敗。 韓国劇的な勝利。 「負けるべくして負け、勝つべくしてかった…」 そんな氣がする。 学級づくりそのものである。 チャレンジタイム 朝の読書 1校時 算数&国語 ・フラッシュカード ・九九 4の段中心 ・10マス計算 ・漢字探し ★ 筆写 「あいうえお」をていねいに、速く書く。 1分間でどれだけ書けるか 挑戦させる。 ちなみに、私は43文字だった。「あいうえおあいうえお」というように書く。 これを、3回くり返す。 1回目は、10書けない子がいた。 「ていねい」に書いているのはいいのだが、リズムがない。 無駄な力が入っているのである。 3回目になると、変わってくる。 これから、じっくり取り組みたい。 2校時 国語と算数 ・辞書引き「に」のつく言葉 ・文章題 今日も、ひねった問題。 避難訓練。 以前に比べ、別人のようによくなった。 目が違う! 3校時 国語と算数 ・文章題の続き ・目の錯覚 ・見るということ ・計測の意味 『長さ』 4校時 国語 音読の様子をビデオ撮影。 みんなで鑑賞。 「まだ地声」 「おもったよりうまくない」 など、厳しい意見がたくさん出された。 もう、自分に厳しくなっている(笑) 私の学級らしい。 5校時 生活科 「植物の不思議」 たんぽぽについての学習。 指名なし発言による話し合い。 |
||||
17日(月) 崩れなくなってきた 全校朝会 4月に比べ、本当によくなってきている。 全体的な崩れは皆無。 授業に入ると、いつもの子どもたちになる。 もちろん、実力ダウンしている子もいるが… 授業態度は、すばらしくよくなった。 1校時 国語と算数 ・フラッシュカード ・九九 4の段 ・10マス計算 ・漢字探し ・辞書引き「な」のつく言葉 ・文章題 2校時 音楽 3、4校時 図工 5校時 算数と国語 ・文章題 ・解釈、ノート指導 ・書き方(問題の解き方) |
||||
14日(金) 決戦の日に チャレンジタイム 朝の読書 1校時 算数と国語 校長先生が、ビデオを撮ってくださった。 ・あいさつ ・フラッシュカード 一斉、個人 ・九九 4の段 ・10マス計算 連続技 ・漢字探し テスト ・表現読み『ふきのとう』『スイミー』 2校時 国語と算数 ・辞書引き「と」のつく言葉 ・『ともこさんはどこかな』 ・文章題 難度を上げる。 3校時 交通安全教室 4校時 道徳 『にじいろのさかな』 前のにじうお→変わったにじうお→今のにじうお について、考えさせる。 まとめを書かせる。 5校時 学級活動 いろいろ、学級の仕事、自分のできることなど。 10マス計算のテスト |
||||
13日(木) 刺激 チャレンジタイム 朝の読書 1校時 算数と国語 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 連続技の導入 ・漢字探し ・辞書引き「て」のつく言葉 2校時 国語と算数 ・表現読みと暗唱 『スイミー』 ・『ともこさんをさがそう』 ・文章題 ひねった問題 かけ算の問題も入れる。 3校時 音楽 4校時 国語と算数 ・解釈と表現『ゆかいに歩けば』 ・文章題の続き 文章の解釈 ・『長さ』の導入 5校時 生活科 『調べる』学習 たんぽぽの秘密についての発表、話し合い。 指名なし発言。 発言内容は、かなり濃い。 生活指導全体会 |
||||
12日(水) 力ある教材 音楽朝会 地声になってしまう…おしい。 1校時 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ・漢字探し ・辞書引き「つ」のつく言葉 2校時 ・表現読み『スイミー』 ラストの場面 ・『ともこさんはどこかな』グループ学習 今日も盛り上がる。 この教材はおもしろい。 迷子捜しに夢中になっている。 「ピンポンパンポーン」(これは、全員でいう) 「迷子のお知らせです。○○さんが、迷子になっています。黄色い服を着て〜」 (問題を出す子) 3校時 ・考える力 ・文章題 ひねった問題 4校時 合同体育 ・基本の運動 ボールを使って キャッチとドリブル、コントロール 今日から、残り勉強。 10マス計算。 といっても5分の居残り。 教育会総会 |
||||
11日(火) 少しずつ チャレンジタイム 朝の読書と歌 1、2校時 図工 空き時間 他の学級で授業させていただく。10分間の国語授業。 6年生の授業を参観。 3校時 算数と国語 ・フラッシュカード ・九九 ・漢字探し ・辞書引き「ち」のつく言葉 ・音読 4校時 算数と国語 ・文章題 ひねった問題 ひねった問題、今日はできた子、今日もできなかった子、様々。 現実は、厳しい。 毎日1問、だんだん慣れていくだろう。 わからない子にとっては、わからない。 ・『ともこさんはどこかな』えらく盛り上がる。 午後 小中合同研修会 |
||||
10日(月) ひねると… 全校朝会、暑さとまぶしさに左右される子、されない子。 1時間目 算数と国語 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 今日から本格的に。 たし算1枚、かけ算1枚 ・漢字探し ・辞書引き 2時間目 音楽 3時間目 国語 辞書引きに続き。 表現読み『スイミー』 「そうだ、みんないっしょに泳ぐんだ」の部分。 『ともこさんをさがそう』 これがおもしろかった。 「限定」と「キーワード」 ゲームをやりながら、知的な力がつく絶好の教材である。 4時間目 体育 ボールを使っての運動。 ドリブルが さまになってきた。 5校時 国語と算数 歌『翼をください』 『ともこさんをさがそう』の続き。 ・2桁の引き算 ・文章題 今日は、ちょっとひねった問題を出す。 一発正解は1人しかいない。
多くの子は、9人と答えた。 なるほど。 「女の子は何人でしょう」なら正解である。 今までやってきた問題は、このパターン。 しかし、今回は一発で答えが出ない。 これがわかっていないと、ひっかかる。 案の定、多くの子がひっかかった。 |
||||
7日(金) 学校公開3 全力で 学校公開最終日。 今日も全力で授業する。 チャレンジタイム 朝の読書 1校時 算数 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ・2桁の引き算 ・文章題 2校時 国語 ・音読『ふきのとう』、『スイミー』 ・表現読み『スイミー』 ・辞書引き 「そ」のつく言葉 ・漢字 筆順、字形を意識して 3校時 体育(合同体育) ・ストレッチ 美しく ・ボールを使った運動 ・ランニングパス 4校時 道徳 『にじいろのさかな』 1時間中、話し合い。 指名なし発言。 たくさんたくさん意見が出された。 ※いずれ報告したい。 5校時 学級活動 「イニシアチブ」 「A市とB市、同じ『きれい』だが、どう違うか」 ※いずれ、報告したい。 4校時、5校時の授業は、とってもよかった。 いずれも、ずっと話し合いが続いた。 たくさんの意見が出された。 追究の授業らしくなってきた。 |
||||
6日(木) 学校公開2 今日も、サークルの仲間が2人参観。 氣合を入れてやる。 チャレンジタイム 読書週間なので「朝の読書」 1校時 算数 ・フラッシュカード…一斉、個人 ・九九 3の段を中心に…一斉、個人 ・10マス計算 ・2桁の引き算 唱和 ・文章題…式、答え、計算 2校時 国語 ・漢字探し A35、B45、C55 ・辞書引き 「せ」のつく言葉 ・音読『ふきのとう』、『スイミー』 ・表現読み『スイミー』 おもしろおかしくやる。 今日の課題は、次のところ。
「うんと」を工夫した子が多かった。 3校時 音楽 4校時 国語 ・『スイミー』表現読みの続き。 2校時、全員いかなかったので、続けておこなう。 「先生、もう一周やりたい!」 (上の)3つの文をつなげて読んだ子がいた。 それを取り上げる。 つなげて読むのは、かなり難しい。 息のコントロールがかなりうまくないとできない、高度な技である。 一息で読まなければならないのだから。 たいがい棒読みに近くなってしまう。 私が見本を見せる。 うまい!(笑) 一人ずつやらせる。 ・『たんぽぽのちえ』 昨日の続き。 さらに詳しく見ていく。 「二、三日」のところをつっこむ。 これがおもしろかった。 かなり高度なので、後半は疲れしまった子がいたが… 5校時 生活科 予定を変更して、『じしゃく』をカット。 全部『たんぽぽ』についてやる。 4校時出されたものを活用。 作文 かなりの材料が出された。 |
||||
5日(水) 学校公開1 学校公開、初日。 サークルの仲間3人が参観。 杉渕学級の父兄はちらほら。 顔を知らない方のほうが圧倒的に多い。 |
||||
4日(火) 無念のリタイア 風邪と疲労でダウン。 このところ高熱が続いていた… 38.5くらい。 さすがに厳しい。 ふらつく、だるい、悪寒 ついにダウン。 久しぶりに学校を休む。 1日中寝ていた。 どうにか、熱は下がってきた。 明日から、学校公開。 休むわけにはいかない。 |
||||
| 3日(月) 休み明けを… 全校朝会 態度がよくなってきている。 休み明けを感じさせない、感じさせる。 両方がある。 以前は、後者オンリーだったのだ。 成長している。 サークルの仲間が参観。 1校時 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ・漢字探し ・音読 ・辞書引き 2校時 音楽 3校時 ・表現読み ・2桁の引き算 4校時 体育 など。 |
||||
| 31日(金) 小さなことだが大きなこと チャレンジタイムと1校時 ・フラッシュカード ・九九 3×6まで。個別指導 ・10マス計算 +4に入る。 簡単なところはちょっとだけ。 +0、1は、1回のみ。同様に、×0、1も1回のみ。 ・漢字探し とうとう100を越える子が出てきた。 ・辞書引き ・音読 『スイミー』 ・文章題の授業 答え方を教える。
昨日は導入のみ。 今日から、本格的に指導する。 間違いは、次のようになった。 A 18 B 18枚 C 18枚多い きちんと答えた子は、 ・赤いおり紙が18枚多い。 ・赤いおり紙が黄色いおり紙より18枚多い。 ・赤いおり紙のほうが、黄色いおり紙より18枚多い。 小さなことだが、大切なことである。 入念に指導する。 正解だった子には、A〜Cの間違い分析をさせる。 間違った子には、教える。 子どもどうしの教え合いもおこなう。 体育 ボールを使って ハンドリングの練習、2人組でパス練習。 道徳&学級活動 ・心をそろえる。 ・給食のおじさんの思い 個人面談 最終日 歓送迎会 基礎固めの2か月が過ぎた。 これからが、本番である。 布石が効いてくるだろう。 |
||||
| 30日(木) 文章題の導入 チャレンジタイム フラッシュカードの活用 ・九九 3の段 3×0〜3×6まで 10マス計算 +4に入る。 以前に比べ、上達のスピードが速い。 力がついてきた ということだろう。 漢字探し A 31個 B41個 C 51個 だいぶ慣れてきている。 蓄積されてきている。 字をていねいに書かせる。 辞書ひき 「こ」のつく言葉 まだまだだが… 意欲あり。 見つけた言葉に線を引く。 マーカーがあるといいのだが… 耳鼻科検診 私がついていれば静かである。 算数 二桁の引き算 松下× 練習させる必要あり。 ひき算ができていない。 文章題 ※初の試み 問題を試写させる。 ・式 ・答え ・筆算 を書かせる。 ノートの使い方 書き方を教える。 しばらく、これをやっていきたい。 少しずつ、レベルをあげていきたい。 答え方は、まだまだわかっていない。 問題に対して正しく答える。 これは必要な力である。 書かせる ・文章題…書き方、ノートの使い方 ・読解…切り口、キーワード、解釈 ※『たんぽぽのちえ』『じしゃく』 ※書くことにより力がつく。 ものの見方が深まる。 ★【歌】大ブレイク しばらくぶりに歌わせてみると… 『歌えバンバン』でも、地声にならなかった。 『友だちはいいな』を歌わせる。 驚くほどうまくなっている。 少し練習すると、ぐんとうまくなった。 部分練習 テーマを決めて練習をおこなう。 音程がよくなった。 声がそろってきた。 響くようになった。 指示通りにできるようになった。 『地球の子ども』もグッド。 教えたところはよい。 あとは、残りの部分の歌詞を覚えればいい。 歌もそうだが… 最近、実力向上著しい。 だいぶよくなってきた。 「形」になってきた。 それが、「歌」という形にもあらわれている。 一人ひとりの成長、向上 クラス全体の成長 相乗効果で、「形」が変わる。 |
||||
29日(水) 追究学習の本格化 今日から、平常モード。 いよいよ追究学習を本格化する。 ・フラッシュカード ・九九 3の段 3×0〜3×5まで ・10マス計算 今日から、+4に入る。 最初にしては、かなりできる。 感覚をつかんできた証拠である。 「家で練習すると、明日10秒切れるかもしれませんね」 ほとんどの子が、プリントを持ち帰った。 さあ、どうなるか? 楽しみである。 ・漢字探し 2回おこなう。 1回目は、いつものように5分間(「5分でいくつ書けるか」) 多い子は、80オーバー 50以上の子が5人。 2回目は、一斉授業。 子どもたち一人ずつ見つけた字をいわせる 私が板書する。 それを、ていねいな字で書かせる。 20+2(この2つは、私が出した)計30漢字を書かせた。 音読 『スイミー』の続き。 「にじいろの〜」である。 初めてやるところでも、ちょっと練習するだけでうまくなる。 力がついてきている。 何より声がいい。 ※この声は、ビデオではわからない。 「生」でなくては… 興味ある方、見にきてくださいね。 追究学習の本格化 『たんぽぽのちえ』 最初のページで氣づいたことを発言させる。 自習のとき、書いているはずなのだが… ・たんぽぽがさく ・春になるとたんぽぽがさく ・春になると黄色いたんぽぽの花がさく ・たんぽぽの花はきれい など。 表面的なものが多かった。 その中で光っていたのは、次である。 ・春になるとあたたかくなってたんぽぽがさく 「春になると」を解釈し、別の言葉に置き換えたのである。 これがいい。 うんとほめる。 コロンブスの卵の話をする。 「あれども見えず」である。 聴けば「なーんだ」ということ。 では、どうして氣づかないのか? 「それでは、冬は?」 ・たんぽぽの花がきれい 「何が『きれい』なんですか。 ・花がきれい ・黄色い色がきれい ・花の真ん中がきれい ・1枚の花びらがきれい ・全部がきれい ・花の形がきれい など、次々に出された。 ・たんぽぽの花びらは、たくさんある。 ・たんぽぽの花びらは、数えきれないほどある。 これを取り上げる。 「いくつくらいあると思いますか?」 100以上と答えた子が多かった。 「大きいたんぽぽと小さいたんぽぽでは、数が違うのでしょうか」 「大きさによって数が違うと思う人?」 少数。 「大きさは、あまり関係がないと思う人?」 多数。 歴代杉渕学級の「追究学習」について語る。 おもしろおかしく(マル秘) 調べることを進める。 さあ、何人が調べてくるか。 もう一つ 「たんぽぽの花とありますね。これは」 A さいたばかり B さいて少したった C 枯れる前 どの花(状態)だろうl。 A 多数、B 少数、C 0 だった。 「だって〜」 といおうとした子にストップを書ける。 「書きましょう」 氣づいたことを書かせる。 →明日、個別指導。 一人ひとりにアドバイスしていく。 辞書引き 今日は、「け」のつく言葉。 実に楽しそうである。 筆算 二桁の引き算 繰り下がりあり。 できない子3人。 追究学習『じしゃく』 はさむの続き。 キーワードと観点 次のように書く子もいうる。 「ぼくは、本をはさんでみました。つきました」 やった内容100に対して、表現されていることは1である。 「厚さ」は、どれくらいなのか 定規で測ってみよう。 「はさめるのは、紙だけか」 ・木(板、机の板) ・ゴム(消しゴム) ・肉(手、耳など) 「材質」に関係なくはさめるのか 同じ紙でも、いろいろある。 ・普通の紙 ・画用紙 ・段ボール など、種類によって変わるのか、変わらないのか。 同じ2センチの厚さでも、1冊の本の場合と5ミリの厚さの本4冊では違うのか? などなど。 このようなことを教えたり示唆したりした。 まずは、ベースづくりである。 体育 合同でおこなう。 前半は、身体づくり。 ストレッチを中心におこなう。 ・見本 ・イメージ語 のセットで指導する。 子どもたちの動きは、がらっと変わる。 びっくりするほど変わる。 美しくなる。 後半は、ボール ボールを使ったグループ対抗リレー 各種。 個人面談 3日目 |
||||
28日(火) 取材 読売新聞の記者 kさん来校。 取材。 授業を見ていただく。 基礎学力づくりの授業 ・フラッシュカード ・10マス計算 ・漢字探し ・言葉探しゲーム(辞書引き) ・音読 表現読み 『じしゃくの秘密』 どんな記事になるのだろうか? |
||||
27日(月) リハビリ 移動教室の付き添いで、3日間教室を空けた。連休明け。 さあ、子どもたちはどんな状態だろうか。 全校朝会、列の後ろに立ってみる。 崩れている子は、いつもの子。 ただし、2人に減った。 グンとよくなっている。 参観者あり。 一日参観 いいところを見せようにも、そんな余裕はない。 3日間の留守を取り戻さなくては。 今日が勝負である。 あいさつ いつもに比べ立つのに時間がかかる。 フラッシュカード、これはいつも通り。 全体でやってから、個人戦。 10マス計算、今日は2枚。 たし算1枚、かけ算1枚である。 やはり…遅くなっていた(特定の子)。 全体的にレベルは上がっている。 しかし、そうでない子は伸びていない。 この3日間の空白は痛い(もちろん、この間も練習してはいるのだが…)。 漢字探し 3つのコースにわける。 30,40,50である。 30いかない子は、再チャレンジ。 終わった子は、私の書いた問題を解く(こちらは、2年生の漢字)。 音楽の授業(専科の先生) 音読 『スイミー』の表現読み。 一人ひとりおこなう。 辞書引き 算数 2桁の筆算 体育 各種リレー 1時間走りっぱなしのリレーである。 何種目やっただろうか。 子どもたちは、くたくたに疲れていた。 「疲れなきゃ体育じゃない!」 トラブル、いずれも給食時 ・けんか ・牛乳こぼし ・お皿わり まあ、当然だろう。 しかし、それ以外はぐんとよくなっている。 |
||||
| 22日〜24日 自分たちの力で 移動教室付き添いのため、自習。 「よくやっていた」(補教してくださったみなさんの話) そうである。 |
||||
21日(火) いわれたとおりに チャレンジタイム ・フラッシュカード チャレンジタイム 全体と個人 できない子は、マンツーでおこなう。 できるかできないか、はっきりする。 ・10マス計算 まだまだ遅い ※子どもによる。 練習が必要。 図工 辞書ひき 言葉探しゲーム 盛り上がる。 今日は「い」のつく言葉。 筆算 二桁の引き算 繰り下がりあり ※難しい。 子どもによっては、全く歯が立たない。 やはり、マンツーマンの指導が必要。 声を出してやらせるが… できない子は、声を出していない。 これは、共通している。 いわれたとおりにやるかどうか… 素直さが勝負のわかれ目 漢字探し 90以上、50以上 平均は、30くらいだろう。 シミュレーション おもしろかった。 明日からの自習準備 子どもたちにやらせてみる。 思ったよりできる。 リズム、テンポ、間など。 私のイメージが入っているような氣がした。 明日の準備 |
||||
20日(月) 今日からあなたも辞書ファン 全校朝会 聴く態度が、だんだんよくなってきている。 あまりかわらない子もいるが… がらっと変わった子が増えた。 育っている証拠。 フラッシュカード、今日は、一人ひとりもおこなう。 これをやると、実力がすぐわかる。 一斉ではごまかせたことが、ごまかせない。 10マス計算 +0、1、2、9、3 ※「3」が思ったより速い。 ×0、1、2、5 ※5の段も速くなってきた。 漢字探し 「5分で35個」に挑戦させる。 多くの子がクリアした。 少ない子で20。最初のころは「0」がいた。 そう考えると、進歩している。 最高は、90。 いやはやすごい。 漢字 2年生の漢字。 算数 二桁のひき算 できない子はできない。 60 − 24 ──── で、0から4ひけないので、逆に4−0をしてしまう。 この手の違いが多い。 一の位に貸した分を忘れてしまっている子もいる。 計算ミスする子もいる。 まだまだ、定着には、ほど遠い。 走・跳の運動 ジャンプ各種、馬跳びリレー、ボールリレー各種、逆立ち、その他いろいろ。 ようやく辞書が届いた。 『小学国語新辞典』(小学館)である。 さっそく、辞書のひき方を教える。 「言葉調べゲーム」 「あい」「アイス」「雨」など、どんどん調べさせる。 今日は「あ」がほとんど。 「おもしろーい」 子どもたちは、いっぺんで辞書が好きになったようである。 今日からあなたも辞書ファン。 たくさんひいているうちに、感覚をつかんでくるだろう。 子どもたちは、辞書ひきが大好き。 4年生からということになっているが… いい物は、1年生から活用させた方がいい。 歴代の杉渕学級は、1年生から辞書を使いこなしている。 6年生よりよっぽどすごい。 何しろ、1年間で辞書がぼろぼろになるくらいなのだ。 これも「生きる力」につながると思うのだが… クラブがあることを忘れ、教室で補教の準備。 大ポカ。ごめんなさい。 ※予定表、1週前のを見ていた。 放課後も、補教の準備。 3日間留守にするので、けっこう大変である。 |
||||
17日(金) 伸びている点、うーんという点 チャレンジタイム ・フラッシュカード ・10マス計算 ・漢字探し 生活科『学校探検』 1年生を案内する。今日は、3、4階、そして校庭。 表現読み『ふきのとう』と『スイミー』 このところ、驚くほどレベルが上がっている。 算数 二桁のひき算、繰り下がりあり。 できる子、できない子の差がものすごい。 後者は、マンツーマンの指導が必要。 体育 合同体育、 各種リレー、馬跳び系、ボール系 1時間走りっぱなし。 『じしゃく』「クリップは何個つながるか」 協力して実験する。 『学校探検』のまとめ ・よかったところ ・説明で難しかったこと ・「よい説明」とは? など、話し合わせる。 |
||||
| 16日(木) 音読 第二段階に チャレンジタイム ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算 ※そろそろ、個別指導に入る。 遅い子の指導 意識の問題 練習不足 ・漢字探し 音読 表現読み 『スイミー』『ふきのとう』 かなり高度な音読へ。 響かせる。 肩を振動させる。 などなど。 『ことばの学習』 漢字編 毎、母、海など これから、2年生の漢字を指導していく。 漢字指導 2年生の漢字 今日から、本格的に実施する。 教科書に出てくる順+よく使う字 むしろ、後者がメインである。 日頃よく使う字からマスターしたほうが効率的である。 たとえば「言う」「話す」「読む」「書く」などなど。 文章を書くときによく使う漢字である。 生活科『じしゃく』 「クリップは何こつくか」 発展→磁力の転移 磁石からはなしても、クリップとクリップがくっついている。 いったいどうしたというのか。 大騒ぎになっていた。 『学校探検』の計画 明日は、2度目の学校探険。 1年生を案内する。 今回は、3、4階を案内する。 自分たちもわからない教室あり。 「学習ルーム」「土器保管室」など。 いったいどうなってしまうのか。 歌『歌えバンバン』 ちょっと目を離すと… すぐ地声になってしまう。 歌う声で歌わせる。 |
||||
15日(水) Oくんの機転 ラジオ体操の指導 ・前回の復習(背伸びの運動) ・新しい技3つ 最初の運動、胸の運動、前後屈のとき腰の支え ・通し(校長先生) フラッシュカード 元氣よく、リズムテンポよく 10マス計算(+0、1、2、9、3) (×0、1、2、5) 漢字探し Yくんが伸びてきた。 音読の練習 そろそろ、本格的な表現読みの指導に入る。 言葉の学級 木下先生が参観。 全体で『ふきのとう』『スイミー』 一人ひとり。 言葉の学級に通っている子は何度もやらせた。 言葉がはっきりしてきた。 「もう、通わなくてもいい」 とのこと。 一人ひとりの実力が見える。 「こわかった、さびしかった。とてもかなしかった」 のいいかた。 4周目 ※最低でも、10種類くらいのいい方ができるように。 教師がどれだけ見本を示せるかが勝負である。 いろいろないい方。 見本を示す。 やらせてみる。→全員 一人ひとりに考えさせる。 見本で示したものから選ぶ。 考える子はオリジナル 1 オリジナル 2 まね 両方価値があることを教える。 カルタ 「スイミーとすい」の掛詞? 数字から変える。 バリエーション。 いろいろ出された。 ・スイミーがすいみんをとる。 ・スイミーがスイカをたべる。 ・スイミーが水泳をしている。 ・スイミーは、すいがらをすてた。 などなど。 ★Oくんの機転 Mさんがいった。 「スイミーが海の水を飲んだ」 「すい」になっていない。 「おしかったね」 「スイミーが海水を飲んだにすれば」 とおくんがいった。 Mさんがいったことを活かしたのである。 「海の水」→「海水」 すばらしい機転であった。 一本とられた。 算数 2桁のひき算 3題 ていねいに書く。 かんたんであるが、間違える子がいる。 『バスの秘密』 書く、発言する。 友だちの考えを聴く→自分意見にする。「活かす」 「活かす」がキーワード 聴くといいことがある。 【パフォーマンス体育】 体育 走・跳の運動 馬跳びリレーのバリエーション 熱くなれ、燃えろ杉渕学級 動きっぱなしで、はあはあ。 距離をとる。→考える体育 どんどんうまくなっていく。 リズムがよくなる。 「音を立てないように」 いい感じになってきている。 集合解散も速くなってきている。 これまた、いい感じである。 |
||||
14日(火) 一人ひとりの指導に入る チャレンジタイム ・フラッシュカード ・九九 ・10マスたし算、かけ算 ・漢字 音読 『スイミー』 『ふきのとう』 いよいよ、一人ひとりの指導に入る。 一人ずつ音読させる。
いろいろな読み方ができる。 私が10通りくらい、見本を見せた。 その後、まねさせる。 5通り。 まずは、まねから入ることが大切。 まずは、1周目、続けて2周目。 1回で終わらないところがみそである。 時間の関係で2周しかできなかった。 10周くらいやりたいところである。 やるたびに読み方を変えなければならない。 かなりハードな課題かな? 算数 百の位、十の位、一の位 歌『さんぽ』 肩を振動させる。 復習 腰の調子が悪く病院へ そのため、5校時の後半は自習。 ※もちろん、補教の先生がついての話。 課題3点 ・表現読み『スイミー』一人ひとり 3周目 ・漢字探し ・カルタづくり |
||||
13日(月) これからが本番 連休終了。 今日から、平常通り。 全校朝会。 今までで、一番並び方がよかった(全体的に)。 崩れる子は、いつも決まっている… その中から、崩れない子が出てきた。 女子は、全員オーケー。 立ち方がきれいになってきた。 ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算(たし算とかけ算) ・漢字探し ・音読 『ふきのとう』と『スイミー』の表現読み。 落差をつけて読ませる。 リハビリの日ということで、お得意のパフォーマンス。 フルコース。 爆笑の連続だった。 少々やりすぎ。 ・漢字探し 10個書けなかった子が、20以上いくようになった。 算数 百の位は○、十の位は○、一の位は○系の問題。 ひっかかる子は、ぐんと減った。 問題にもよるが、2〜3人である。 ひっかけ問題
全員正解、9 しかし… 「全員違います。正解は『サイボーグ009』です」(笑) 「先生、ふざけないでよー」 「だれですか、ふざけているのは」 「先生です」 バスの秘密 体育 馬跳びリレーのバリエーション、障害物リレーのバリエーション 各種。考えないとできない技ばかり。 |
||||
10日(金) 連休の狭間で 3 チャレンジタイム ・フラッシュカード ・九九 ・10マス計算(たし算、かけ算) 漢字探し 裏技を教える。 「前やったのを見てもいいです」 今の段階では、これでいい。 ていねいにたくさん書くことが大切。 毎回少しでもいいから、書く数が増えるようにしたい。 算数 一の位、十の位、百の位 たとえば、次のような問題である。
これは、すぐにできる。 読んだ順に数字を書けばいい。 562 しかし、ちょっとひねるとできなくなる子が出てくる。 昨日教えた方法を使わない子ができない。
これを、328 としてしまうのである。 順番を変えてやる。 十の位は、○、百の位は○、一の位は○ 一の位は、○、百の位は○、十の位は○ などなど。 少し練習したところで、またしてもひっかけ問題。
見事にひっかかった子がいた。 「032」としたのである。 「先生のいったように、 百|十|一 の図を書いてやったから間違えたんです」 「とてもいい間違いです」 とほめたあと、指導する。 「032、電話番号だったらいいですけど、この場合は『32』ですね」 次なる問題。
一人だけ、ひっかかった。 「000」 学校探険 1年生を案内する。 合同体育 ・着地の基礎 ・音を立てない。 まずはその場で。 ジャンプして着地。 見本を示す。 膝の使い方、つま先 舞台の上から飛び降りる マット使用する。 飛び降り→ウサギの足打ち3回→動物歩きと連続させる。 ミックス走 膝を使ってやわらかく。 ・腕支持の練習。動物歩き各種 右手を出したときに右足を出す。 右手を出したときに左足を出す。 いろいろなパターンをやらせる。 音読 【表現読み】 『ふきのとう』うねり、流れ 『スイミー』 うねり、流れ 高度な技術である。 板書が効果的だったように思う。 強弱を視覚化する。 ← たい け び ど そ あ このように板書する。 視覚的にわかりやすい。 全員でやると、形になっている。 もう少し練習し、体にしみこませたい。 聴き合うとは? カルタ 創作活動 人として 好きな子の名前を聴く 「絶対にいわないから」 といったにもかかわらず、みんなにふれ回る。 男らしくない行為である。 母の日特集 お世話になっている人に感謝する。 意識を向けさせる。 「やってもらってあたりまえ」→「ありがたい」 テーマ日記を書かせる必要があるだろう。 子どもたちの状況 私がいれば静かにできるようになった。 いないと… 前は、いても静かにならなかった もたなかったのだから、大きな進歩である。 私のいるときいないときの落差が大きい。 内科検診 男の子の番 プリント印刷のため、教室を空けたとき まあ、休み明けということもあるだろう。 |
||||
| 9日(木) 開校記念日 |
||||
8日(水) 連休の狭間で 2 連休の狭間ではあるが… 子どもたちは、平常通り。 ゴールデンウイーク前半の休み明けとは、えらい違いである。 「勉強しよう」という顔である。 音楽朝会 『さんぽ』と『校歌』 講師の先生が伴奏してくださる(上手で感激)。 「歌う声で」 久しぶりの音楽朝会。 地声に戻っている学年あり。声の出も悪くなっている。 全体指導、各学年指導を使い分ける。 アップテンポでやっていく。 いい学年は、何度もやらせる。ほめる。 やるたびに、声がきれいに響くようになっていく。 見る見る変わっていく。 とくに4年、6年がいい。 わが2年生は…まだまだ。 1年生も、ていねいに歌っている。 いい感じである。 フラッシュカード ・数をいう。 ・+1の数 ・+2の数 ・+9の数 ・×2 ・×5 10マス計算 +0、+1、+2、+9 ×0、×1、×2、×5の前半 漢字探し(くり返しよる向上) 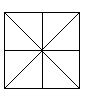 5分間。 「もっとやりたい」という意見が圧倒的。 時間を延長する。 今日は、納得するまでやらせた。 わからない子のために、漢字を板書していく。 100以上見つけた子、最高は130! すごい数である。 クイズであり冒険課題(?)のようでもある。 「ていねいに書く」ことが条件。 子どもたちは、毎日たくさんの漢字を書いている。 漢字練習の意識なく、漢字練習をしているのである。 カルタ(創作活動) ・自由課題 ・共通課題 この両方が大切。 五分五分ということではない。 両者のバランスをどう取るか、腕の見せ所である。 後者は「千」 子どもたちが考えたもの ・せんせいが千人 ・仙人が千人 ・洗たくもの千枚 ・せんべい千枚 ・山手線千台 ・すみません千回 その他たくさんだされた。 音読『ふきのとう』 表現読みをさせる。
あとの文は「と ざんねんそうです。」となっている。 残念そうに読まなければならない。 子どもたちは、さらっと読んでしますう。 粗くいって、3つのグループにわかれる。 ・意識していない。 ・意識しているのだが、上手く表現できない。 ・意識して表現している。それなりに表現できる。 真ん中の子が多い。 まだ、声をコントロールできないのである。 算数 「ぼうやいろがみの数を、数字でかきましょう」 実力差がもろに出る。 注意力の差である。 普段の態度とイコールなのがおもしろい。 間違う子は「よく見ていない」のである。 ひっかかったのが3番(2人)。 百の束が3つ 折り紙が5枚 これを「350」としてしまったのである。 百の位の次は十の位と思いこんでいるのであろう。 見直しもしない。 百 十 一 ┣━━╋━━╋━━┫ このような図を書かせる。 それぞれの位の下に数を入れさせた。 続いての問題 (1)100を4こ、10を8こ、1を5こ合わせた数は□です。 (2)100を5こと、1を9こ合わせた数は□です。 (3)325は、100を□こ、10を□こ、1を□こ合わせた数です。 (4)630は、100を□こと、10を□こ合わせた数です。 これは、よくできていた。 問題の問題は次である。
間違える子が出てきた。 前述した図を書かない子である。 毎回きちんと書いた子はノーミス。 ・265 出てくる順に書いたのである。 ・566 ・652 もう一度、図(上図)を書いて考えさせる。 百 十 一 ┣━━╋━━╋━━┫ 5 6 2 このように、確認しながら書けばミスは少なくなる。 これを「手で見る」という。 いい加減にやったり、めんどくさがってやったりするからミスするのである。 「めんどうくさい」を一掃しなければ。 字形 ていねいに書かせるが… このときはていねいに書く。 しかし、漢字練習、刈る田づくり、作文になると、雑になる子がいる。 「字の練習の時だけていねいに書けばいい」とでも思っているのだろうか。 字の練習をしたら、それを活かすべきである。 今、そのことを教えている。 『バスの秘密』 氣づいたことを書かせる。 『学校探検』 金曜日、1年生を案内する。 基本的には、一対一である。 どうガイドするか 考えさせる。 シミュレーションさせる。 |
||||
| 7日(火) 連休の狭間で 連休が終わった… とはいえ、新河岸小はまだ終わっていない。 9日が休み。 2日学校、また休み。 リズムがつくりにくい。 7日(火) 学校 8日(水) 学校 9日(木) 休み(開校記念日) 10日(金) 学校 11日(土) 休み 12日(日) 休み 5月7日 再スタート チャレンジタイム ・フラッシュカード 声が大きい。 休み明けとは思えない声である。 ただし、姿勢は崩れている子もいる。 ・九九 5の段を教える。 一通り教える。 答え(の1の位)が、0か5になることを教える。 すべてにおいて、こつ、ポイントがあることを教える。 今日は、×0、×1、×2まで。 狭間の期間ではあるが、すべて同じことでは刺激がない。 そこで、新しいことを入れたのである。 ・10マス計算 大差がついてきている。 そろそろ個別指導の必要。 こちらも、+9に入る。 こつを教える。 「0」以外は、十の位に1を書く。一の位にその数より1つ下の数を書く。 例 3だったら、十の位に1,一の位に2、「12」とするということ。 覚えれば簡単。 訳がわかった子は、急に速くなった。 漢字 例の問題 ※前回、みんなで100見つけた。 5分でどれだけ書けるか テストする。 字をていねいに書くように指示する。 ちなみに私は、80以上書いた。 多い子は、28個だった。 ていねいに速く書く。 繰り返すことによって、どんどん覚えていく。 2回目、50をオーバーする子が出た。 58個が最高。 4人が50以上。 繰り返すことにより、意識が高まる。 やるべきことも明確になる。 先ほどやっているので、感覚が戻ってきている。 一番少ない子で50見つけたら、終わりにしてもいいだろう。 まあ、当分先の話である。 音読『ふきのとう』 全員で読む。 ものすごくきれい。 2年生とは思えない声、響きである。 実際に聴かないとわからないだろう。 ※聴きにきてくださいね(笑) しかし…一人ひとりになると、あやしくなる。 ・読むべきところがわからない子 1人 ・すらすら読めない子 3人 これからは、一人ひとり。 5月の課題は、個別指導であろう。 一人ひとりをよーく見て指導すること。 カルタづくり 創作活動 遊びながら言語感覚を磨く 教科書に載っているのを読ませる。→考えさせる。 わからない子も、やっているうちにわかってきた。 「いちごが1つ」 「しじゅうからが四わ」 「にくまんが2個」 などなど。 おもしろい。 きょうは「一」など、限定してもいいだろう。 辞書を引いてもいい(まだこない)。 いろいろとやってみたい。 算数『3けたの数』100より大きい数をしらべよう これは、できがよかった。 くどくど説明せず、問題をやらせる。 説明より問題を解いた方がいい。 153 614 509 760 800 100を5こ、10を7こ、1を2こ合わせた数は? 終わった子には、自分で問題を創るように指示する。 生活科 『バスの秘密』 遠足の帰り、バスに乗った。 そのバスの秘密をさぐる。 『ふきのとう』と同じように氣づいたことをいわせる。 書かせる。 明日から、つっこんだ見方を指導していく。 復習 10マス計算、 漢字をていねいに書く。 ひらがなの書き方。「お」「み」「い」など。 今日教えたのは「ん」 ポイント ・縦勝ちと横勝ち 口は横勝ち、日は縦勝ちなどなど。 六の下の部分 活字だと八のようになっているが。 貝の下も同じである。 右の部分をしっかり止める。 しかし、一人一人を見ていくと、指示通りかけた子は半数だった。 残りは「できたつもり」になっている。 「これでいい」「自分はできた」と思っている。 違いがわからないのである。 見えていないのである。 給食準備、片づけは、はやくなってきた。 掃除は、机ふき、壁ふきなど。 私が買ってきたソフトクレンザーを使わせる。 子どもたちにまかせるとすぐなくなってしまうので、私が一人ひとりに一滴ずつ進呈する(笑) 歌 『さんぽ』一発で合格。 |
||||
2日(木) 遠足 今日は、遠足。 絶好の機会である。 ・今までやってきたことが活かされるか。 ・今日の課題 ・今日入れること。 連休の狭間、キツイかなという感じもしたが… どうしてどうして、子どもたちはよくやった。 今までやってきたこと ・集合、解散 ・整列 ・話の聴き方 ・態度 ・私語 ・反応 ・ゴミ拾い 今日の課題 ・なかよく遊ぶこと ・なかよく食べること ・ひとりぼっちの子をつくらないこと ・1年生のめんどうをみる。 ・荒川土手の自然を見つける。 ・公園で、自然を見つける。 ・バスの秘密を見つける。 ・「疲れたー」「暑い」などといわない。 |
||||
| 5月1日(水) 連休明け 2日目 連休明け2日目。 さすがに昨日とは違っていた。 30日(火)休んだ子が、目立つこと目立つこと。 1日の差は大きい。 体育朝会 私の担当は、ラジオ体操の指導。 今日は、背伸びの運動のみを指導した。 短時間で、子どもの動きが変わった。 美しくなった。 意味、ポイント、やり方を教えたのである。 1時間目 ・フラッシュカード ・10マス計算(たし算とかけ算) ・音読『ふきのとう』と『スイミー』 一人ずつ読ませる。意識の違いがよくわかる。 読むところがわからない子もいた(笑) 算数 筆算と「合わせて100になる数」 国語 『ふきのとう』の読解。指名なし発言。 発言は、ばんばん飛び出す。 3分の1の子。 内容もおもしろい。 1人1言は、いわせる。 生活科 『じしゃく』 「水の中でもじしゃくの力は変わらないか」 体育 ジャンプ、馬跳び、着地、前まわりなどなど。 グループごとに動く。練習する。 ローテーション。 音がしないように馬跳びをしてみよう と、課題を出す。 つま先、ひざがポイント。 踏切版とマットを使って、ジャンプと着地の練習。 音がしないように着地する。 「どうしたら音がしないか」考えさせる。 研究推進委員会 |
||||
| 30日(火) ずっと休みにしてほしい 三連休明け。 体調を崩し休んだ子2人。 リンゴ病の疑いで相対した子1人。 旅行、キャンプなどで疲れ切っている子もいた。 ずーっと休みの方がいいのだが… 授業は、軽め。 しかし、それでもキツイ子にはキツイ。 休み明けは元に戻っている。 大変な子ほど、すぐ元に戻る。 食管をひっくり返したり… 離任式 私がそばにいれば、何とかもつ。 それぞれの先生の話はよかったのだが… 何せ7人。 1時間近くかかってしまった。 連休明けに長時間は厳しい。 PTA歓送迎会。 新人代表でSOHRANを踊る。 |
||||
26日(金) 頭の使い方 チャレンジタイム ・10マス計算 たし算 +0、+1、+2 ・10マス計算 かけ算 ×0、×1、×2 2の段、だいぶ速くなってきた。 ・音読 『ふきのとう』、『スイミー』 これからは、個別指導を入れていく。 筆算 二桁のたし算、頭の使い方 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 について教える。 難しそうに見える計算も、考え方によっては簡単になる。 頭の使い方、工夫 100−7 100を99+1として考える。 そうすると、くり下がりがない。 簡単にできる(はず)。 ただし…1桁のたし算がぱっとできないと話にならない。 基本的なことができるようになるまで、まだ時間がかかりそう。 国語『ふきのとう』の読解 「よいしょ、よいしょ おもたいな。」 竹やぶのそばの ふきのとうです。 について書かせる。 はやくも、ノート1冊終わった子が出てきた。 はやい子は、字もきれい。 これが不思議である。 やる氣、意識が違う。 漢字の成り立ち。 「大」 1日、1つずつ教えることにした。 カードづくりにするか、ノートにするか 両方か? 考え中である。 字形 昨日の復習「る」 「る」のポイント 上の線を短く、中心から。 長い坂 下の○は三角に「おむすび」 認識してもできるとは限らない。 しかし、意識してやるかどうかは、ある意味で決定的な違いを呼ぶ。 後々その違いがわかってくる。 今は、布石の段階。 合同体育 基本の運動 いろいろ 馬跳び リズム体操 ジャンプ トレーニングなど リレー 1時間ずっと運動させる。 集まり方、さっと集まり体育座りなd、集団行動について教えている。 これができるようになると、すべての面でよくなる。 道徳の授業 川村先生(隣の学級の先生)にいただいた資料を使わせていただく。 「明日は遠足、うれしいね」 A そんなにうれしい? B うん、うれしい! C まあね。 それぞれについて、考えさせる。 A あんまりうれしくない。 聴いた人ほどうれしくない。 遠足が楽しみじゃない。 あまり行きたいと思っていない。 みんなとお弁当を食べるのを楽しみにしていない。 聴いた人が、いやな氣持ちになる。 B すごくうれしい。 はやく明日にならないかなって思っている。 にこにこして答えている。 みんなと一緒に行くのが楽しい。 わくわくしている。 聴いた人がうれしくなる。 聴いた人と同じ気持ち。 C Aの人よりはうれしいけど、Bの人よりはうれしくない。 てれているのかもしれない。 なんでも「まあね」という人。 ふつう。 遠足にいっても行かなくてもどっちでもいい。 などなど、その子の価値観が見えておもしろかった。 学級活動 連休の過ごし方、遠足、その他いろいろ 『じしゃく』つくか つかないか 相変わらず、盛り上がっている。 Hくんは、50以上見つけている。 教室を飛び出し、廊下、他の教室で実験している子もいた。 きわめつきは、トイレ。 運がつく? 復習 10マス計算(たし算、かけ算) 子どもの能力差が大きい。 書く力は段違いである。 下の子を引き上げる必要あり。 まだ、ぼーっとしている。 取りかかりがよくない。 とはいえ、スタート時に比べると10倍以上はやくなっているのだが… 字形の研究 子どもたちに教えるために、久しぶりに字の本を開く。 どう教えるかの研究である。 |
||||
25日(木) 予測 予想 応用 チャレンジタイム ・フラッシュカード ・10マス計算 たし算 +0、+1、+2 ・九九 2の段 ・10マス計算 かけ算 ×0、×1、×2 ・音読(表現読み)『ふきのとう』『スイミー』 新しいところを扱う。 少しずつつけ加えていく。 そろそろバージョンアップ。 そして、個別指導に入る。 算数 筆算 予測 予想 応用 見た目にだまされない。 原理がわかれば、桁が多くなってもできる。 同じようにやればいい。 そのことを教える。 83+46 62+74 27+91 これからが本題 125+375 318+682 2579+7421 子どもたちの集中度、熱中度が違う。 えらく盛り上がった。 難しいことに挑戦するのが人間。 手が届きそう 難しそう、でも、やってみたい。 できた! これをやることによって、2桁のたし算の習熟度が上がる。 国語 『ふきのとう』の読解 「どこかで、こえがしました。」 について書かせる。 視写 視写どころではない子が多い。 字形がわかっていないのである。 たとえば「み」 上の部分は、中心線に乗せるのだが… できていない。 というか知らない。 「お」縦線を真ん中に書いてしまう、などなど。 1から教える必要性を感じた。 まずは、ポイントを教えたい。 さっそく、1から教える。 視写はお預け。 追究学習 『じしゃく』 おもしろい。 どんどん実験する。 書くことがおろそかにならないようにしたい。 Hくんは、よく書いている。 30以上も書いた。 実験と書く この両輪が必要。 私の机の引き出しの中からグッズを出し、すべて実験していた。 ★家庭学習につなげる 学習を広げる。 家でやってみようと働きかける。 家庭学習ということを入れる。 ノートを用意するといい。 どれくらいの子がやってくるだろうか。 学校探険の計画 さっそく、実行していた。 休み時間に学校探険の下見をしていた。 行動に移るのがはやい。 10マス計算 ・手が早く動かない。 ・頭が遅い。 ・頭と手の連動ができていない。 ようは、トレーニング不足なのである。 まだ、コップに水がたまっていない。 水があふれるまで、簡単な問題に取り組みたい。 もう少しである。 漢字 漢字クイズ 古代文字を示し、字を当てさせる。 成り立ちを教える。 手のひらの上はここだと上の文字 →ノートに書かせる。 カルタをつくらせる。 どうしたらいいかを考えたい。 漢字のユニットを構築したい。 教材研究をしなければ… 3段階方式 → → → 入れる 慣らす マスターさせる 新しいものを入れる。 その前に入れたものを慣れさせる。 前の前に入れたものをマスターさせる。 |
||||
24日(水) 先を読んでの行動 チャレンジタイム ・フラッシュカード ・10マスたし算 +0、+1、+2 ・九九 2の段 ・10マスかけ算 ×0、×1、×2 ・三色音読 『たんぽぽ』『ふきのとう』『スイミー』 ・歌『さんぽ』 1年生を迎える会 算数 虫食い算2 国語『ふきのとう』 解釈 「雪がまだすこしのこっていて、あたりは しんとしています」の部分。 Mくんは、しっかり元に戻っていた(笑) これを学術用語で「まぐれ」という。 そう簡単にはいかない。 いつも書かないYくんが、1つ書いた。 指名なし発言 上の内容 ・雪が残っている。 ・まだ、冬。 ・雪は、凍っている。 ・雪は、粉雪。 ・雪は、固くなっている。 ・雪があるとことの方が多い(絵を見て)。 ・雪の下に、ふきのとうがある。 ・雪の下で動物たちが冬眠している。 ・太陽の光で、雪がとけ始めている。 ・雪は、やわらかくなっている。 ・雪がとけて水になって、水たまりができている。 ・雪がとけたところは、土になっている。 ・竹やぶは、すごく静か。 ・まわりは、しーんとしている。 ・あんまり音がしない。 ・全然音がしない。 ・朝早いので、まだみんな寝ているのかもしれない。 ・みんなが寝ているから静か。 などの意見が出された。 生活科 追究学習『じしゃくの秘密』 今日から、やり方を変える。 自由にやらせると、遊びで終わる子が多い。 授業のまとめが、「○○をして遊んでおもしろかった」になってしまう。 切り口がシャープな子の課題を、共通のものにする。 初回は、次の通りである。
作文用紙を配る。 ※生活科ノートがある子は、その限りではない。 1 つくえ ○ 2 消しゴム × このように書いていくように指示した。 子どもたちの動きは、がらっと変わった。 見事!というしかない。 「先生、椅子の足にくっつきました」 「机にくっつきました」 「ロッカーに、くっつきました」 「ちょっときてきて」 などなだど、子どもたちは次々に報告にくる。 そして、それを書くのである。 やることが明確である。 「これでよし」がない。 教室には、試してみるものがたくさんあるから。 報告を聴きながら指導する。 「ついたのは、机のどこですか。上ですか、横ですか〜」 「上です」 「そうですか、上なんですね。横はつくと思いますか?」 こんな感じで、細分化した見方を教えていく。 大雑把な見方だと「つくえ」でひとくくしてします。 細分化した見方だと次のようになる。 つくえの上 横 足 右の前、右の後ろ〜 体育 馬跳びを中心に。グループ対抗でおこなう。 ・馬跳び 横 縦 ・ブリッジくぐり ・トンネルくぐりいろいろ ・ジャンプ ・大ジャンプ ・カエル倒立 ・ウサギの足打ち ・倒立 ・側転などなど 先を読んでの行動 例 体育のあとは給食、4時間授業 ↓ 机をグループの形にしておく。 ↓ 帰りのしたくをしておく。 ↓ 体育が終わったら、当番はすぐに着替える。 チャレンジタイムなども同様。 「次は何をやるか」がわかる。 ↓ あらかじめ準備する。 1年生を迎える会でもおこなった。 「次、『立ってください』というよ。いわれる前に立っちゃおう」 などなど。 給食準備に着手する。 ようやく… まだ、おしゃべりが多すぎる。 口に意識がいくと、手が遅くなる。 掃除 箒はまだ持たせない。原則として。 雑巾掛けから入る。 雑巾を投げた子(2人)、3回目に厳しく叱る。 見つける子は、きたないところを次々に見つけるようになってきた。 私は、窓ガラスのサッシの部分をきれいにする。 10年くらい拭いていない? ものすごくきたない。 クレンザーを使うとよく落ちた。 毎日、少しずつやっていきたい。 大化けの兆しは… ひっこんでしまった(笑) 人生そう甘くない。 |
||||
23日(火) 大化けの兆し チャレンジタイム(8:35〜8:45) ・フラッシュカード +1、+2 ・10マスたし算 +0、+1、+2 ・九九 2の段 ・10マスかけ算 ×0、×1、×2 ・三色音読 『たんぽぽ』『ふきのとう』『スイミー』 ・歌 15分で6種目、かなり密度が濃い。 力は、着実についてきている。 1、2校時 図画工作(専科) 5年生の補教、昨日の続き(表現読み)をおこなう。 「はずかしい」という意識について語る。 全員が読んだ。 その後、10マス計算。 おもしろおかしくやる。 とても反応のいい学級。 2日間、楽しかった。 2年2組歌の指導、ついでに音読も。 声がきれいで上手である。 下手な子、やる氣のない子がいないのがすごい。 教えれば、ものすごくうまくなる可能性を秘めている。 2年生、これからが楽しみ。 算数 筆算 虫食い算 「考える算数」 虫食いのところの数当て。 正解の子は、解法を説明させる。 間違いの例を出し、どうして間違えたのかを考えさせる。 間違えた子のほとんどが、くり上がりの「1」を忘れていた。 国語 『ふきのとう』
この部分について、氣づいたことを書かせる。 Aくん、書きも書いたり。 なんと、40も書いた。 もう、ノートがなくなってしまい、後半は原稿用紙に書いていた。 給食の待ち時間、給食後、休み時間もやっていた。 いつもとえらい違いである。 ねばり強く取り組んだ。 「もうやめたら」 といっても、きかない。 「やる」 と一蹴されてしまった。 大化けする可能性あり。 Mくん、今日は字をていねいに書いた。 しかも5ページ。 すぐ疲れてしまう彼が… この集中力、持続力はどこからくるのだろうか? はやくも大化けする子が出てきた。 考える 「どうしたら馬跳びがうまくいくか」 昨日やった馬跳び。 うまくいかなかった。 その原因と対策。 出された意見 ・『ぜったい跳べると思う」ことが大切 ・くっつかない。 ・くっつきすぎない。 ・間を1メートルあける。 ・勢いをつける。 ・頭を中に入れる。 ・足首を持つ。 などなど。 漢字の成り立ち 絵文字→古代文字を書いて、今の字を当てさせる。 簡単なものから、難しいものまでいろいろ。 雨、貝、火などはすぐにわかった。 以外だったのは「月」 これがわからなかった。 熱心な子は、全部ノートに書いていた。 このへんが伸びる秘訣だろう。 この子は、『ふきのとう』の読解でもがんばっていた。 1つのことで、ノート1ページ書いた。 磁石の実験、まとめを書く。 作文は… 1から指導する必要あり。 しかし、きらりと光る文章を書く子、切り口がいい子もいる。 明日から、少しずつ指導していきたい。 しばらくは、共通課題の方がいいだろう。 復習…10マス、音読、歌、漢字、『ふきのとう』、虫食い算 そして、「考える体育」 さようならをしてから校庭へ。 5分ほど、馬跳びのグループ練習。 さっき話し合ったことを実際にやってみるのである。 頭と体 頭と行動 が違うのがおもしろい。 |
||||
22日(月) 第2クールスタート 今日から、第2クール(2週間で1区切りにしている) とはいけ、休み明けなのでリハビリが中心。 休み明けの朝会、実力がもろに出る。 きちんとしている子、崩れる子にはっきりとわかれる。 フラッシュカード いろいろ 10マス計算 +0、+1、+2 今日から、いよいよ+2に入る。 大喜びしている子が圧倒的に多い。 九九 10マス計算、かけ算 ×0、×1、×2 音読『たんぽぽ』『ふきのとう』『スイミー』 歌『さんぽ』 『友だちはいいな』知っているというので、歌わせる。 まだ、声が出ない。 いい声が出る歌なのだが、いまいちである。 きちんと覚えていないからだろう。 音楽 講師の先生による授業、1回目。 その間、補教。 学習法、表現読みを教える。 文章題の解き方 私が見本を見せる。 板書したことを写させる。 まずは、まねから。 『ふきのとう』の読解 3回目。
よくわからない子に対して、私の考えを書いていく。 まねさせるのである。 見つける子は、自分で見つけていた。 パフォーマンス体育。 今日は、馬跳びが中心。 メインは、グループごとに作戦を練るところ。 →「考える体育」 「考える」練習 今日は、漢字「三」の書き方についておこなう。 |
||||
19日(金) 検査でわかる成長度 じしゃく もりあがっている。 朝から、じしゃくを使って実験していた。 九九 10マス計算 読解の2回目 今日は、個人で書かせる。 ブレイクした子は、20以上書いた。 聴力検査 今日は静かだった。 検査の度に成長している子どもたち。 ○○検査で、成長度がわかる。 ・姿勢 ・態度 たとえば ・きちんと並べるか ・まっすぐ並べるか ・さっと並べるか などなど。 漢字&書写 打ち込み、止め、払いなど、基本的なことを教えている。 マンツーマンである。 子どもたちの字は、ていねいになってきた。 しかし…作文を書かせると振り出しに戻ってしまう。 漢字は漢字、作文は作文なのだろう。 この2つが連動していない。 次は、「つなげる」作業が必要。 『ふきのとう』 解釈の2回目
氣づいたことを書かせる。 ポイントをつかんだ子は、どんどん書いた。 20以上見つけた。 「氣づいたことを、先生に教えてね」 一方、書けない子もいる。 一行も書けない。 まあ、これが普通なんだけどね。 アドバイスする。 音読、3つの教材、3つの読み方 最初にくれべ、劇的に変化している。 聴いたらびっくりする。 それくらい違う。 声がそろってきたし、きれいになってきた。 強弱のつけかたは、すごい! 緩急もつけられるようになってきている。 子どもたちの急成長にびっくりしている。 合同体育 基本の運動 1時間中走らせる? 体育着は、砂だらけ。 運動量は、ものすごく多い。 道徳の授業 協力 「筆算」と「じしゃく」の授業を通して、協力ということを教える。 一斉A部会のため、4時間授業 |
||||
| 18日(木) 追究の授業 生活科は、追究の授業をする。 例にあげた「じしゃく」が、早くもブレイク。 喜んで実験をはじめた。 「たすと100になる数」の2回目。 個人学習→グループ学習。 この意味を教える。 ノートをきれいに書く指導も並行しておこなっている。 『ふきのとう』昨日出た意見を写させる。 ノートの使い方を教える。 わからない子には、私が途中まで書く。 |
||||
| 17日(水) 概念くだき 概念くだき 「見方・考え方」 ドラえもんの四次元ポケット 題材『ふきのとう』 冒頭の一文を扱う。
氣がついたことをいわせる。 「なんでもいい」といったところで、意見が出るはずもなし。 例を出す。 「夜が明けた。 」 1 夜が明けた。 2 月がしずんで、お日様が出てきた。 3 朝日がのぼった。 4 暗かったのが明るくなった。 5 夜から朝になった。 6 夜はさむかった。 7 光をあびている。 8 太ようの光をあびている。 9 太ようの光で雪がとけてきた? 10 夜のうちにこおってしまった。 11 まわりがあたたかくなってきた。 12 さむくて暗い→明るくてあたたかい。 13 夜のあいだに、雪が少しとけた。 14 天氣がいい。 15 はっぱやふきのとうがしめっている。 16 朝の光で雪がとけていく。 17 朝になって、あたたかくなってくる。 18 下(地面)は、しめっている。 19 もう雪はふっていない。 20 雨もふっていない。 なんと20も見つけた。 最初にしては、すごい。 似たようなものもあるが、今はどうでもいい。 たくさん出すことが大切なのである。 子どもたちは、びっくりしていた。 それはそうだろう。 わずか一文から、こんなにたくさんの意見が出されたのだから。 あれども見えず」から→見えるへ これぞ、ドラえもんの四次元ポケット。 見方・考え方 枠をはずせば、発言できる。 「空の色は、青」 ではない。 概念をくだく。 作文の会でいう、「概念くだき」である。 こうなると、国語の授業がおもしろくなる。 いくらでも見つかるからである。 「細分化」、「100倍細かく」の手法である。 イメージもふくらんでくる。 音楽朝会 音楽の先生1ヶ月の療養のため、私が代わりに指導することになった。初めての指導である。 下地ができている。 歌う声がすぐ出せる。 やる氣がないクラスは、あまりない。 そこそこできる。 今後の成長が楽しみである。 『さんぽ』を指導する。 声の出し方、響かせ方など 学年ごとに指導する 期待がもてそう。 音読 3つの教材文を読みわけ 『たんぽぽ』 表現読み、口をはっきりあけて 『ふきのとう』やさしい読み方 『スイミー』 メリハリ 『たんぽぽ』
教えたこと ・ちょうちょうは、上から見ている。 ・まぶしそうにしている。 ・相手に語りかけている。 ・「うふん」の工夫。 『ふきのとう』
教えたこと ・やわらかく読む。 ・さわやかに。 ・明るくなった感じを表現する。 ・「ささやいて」内緒話のように読む。 ・声の大きさを変える。 ・「あたり」で、周りを見る。 ・「しん」のいい方。 『スイミー』
教えたこと ・「広い海の」声を広げる。 ・「どこかに」どこかわからないという感じを出す。 ・「小さな」ささやくように読む。 ・「楽しく」楽しそうに明るく。 ・「みんな赤いのに」スピーディーに読む。 ・「一ぴきだけは」強調する。ゆっくりはっきり ・「からす貝よりも、まっくろ」スピーディーに読む。 速→遅→速(緩急) ・「およぐのは、だれよりもはやかった。」自慢して、素早く。 ・「名まえは」の後、うんとためる。 ・「スイミー」 アナウンサーのコールのように読む。 一人ひとり 今日は、希望者のみ「やりたい」といった子 発表した子のいい点をほめる。 算数 筆算 考える力をつける。 昨日の復習から。 10 + 90  ̄ ̄ ̄ ̄ 100 これをやらせた後、課題を示す。 「たして、100になる数を見つけよう」 「5つ以上見つけよう」 学習のステップを確認する。 ・自分でやる ・友だち・先生に聴く ・教科書を見る わからない子には、ヒントを出す。 例 20+80、逆もできることを教える。 80+20 85+15、98+2、73+27などなど。 漢字というより書写指導 マンツーマン指導 マンツーマン。 「教師対子」の構造になっている。 これがいい。 私もじっくり見ることができる。 そのとき、一字のみを指導。 ポイントを教える。 ・45度の打ち込み ・バランス など。 普段やらなかった子が、最後まで集中してやっていた。 1回の指導は短く、何回もおこなう。 たとえば「三」 ・3つの線の長さ ・各線の間隔 ・線の形態(一番下の線は、ふせ) 順番 「一」→「二」→「三」→「四」→「五」→「六」→「七」 →「八」→「九」→「十」 一つほめ、一つ指導という感じでやっていった。 パフォーマンス体育 いろいろな運動をおこなう。 基本の運動である。 4列、赤白男女別 アザラシ歩き、クモ歩き、ウサギ跳び、その他いろいろ。 おもしろかったようである。 ストレッチ 筋肉、筋 意識してやらせる。 「今、ここの筋がのびています」 「この筋がピーンと引っ張られています」 「ここが、痛いはずです」 最後は、側転。 指示一つで、格段にうまくなる。 「遠くに回りなさい」 「できないもん」 A子さん、どんなことでも飛び出すこのせりふ。 あまったれでわがまま。 「Aさんを教えてくれる人」 男の子が教えてくれた。 この方が、いうことを聴く。 フラッシュカード +0、+1、+2 テンポよくおこなう。 全体で。 +2でも、リズムをくずさなくなった。 個人でもやらせる。一人につき3問くらい。 九九 2の段、今日は2×9までいわせる。 順番通りだけではなく、バラでもやらせる。 アトランダム 全→個人でもやらせる。 歌 『さんぽ』 「あるこー」 の部分を指導する。 主に「響かせる」指導である。 かなり響くようになってきている。 のばす 上にもっていく 教室中に広げる。「元氣玉をつくろう」「声のボールを大きくしよう」 「教室いっぱいにしよう」 『地球の子ども』 「太陽の子ども 宇宙の子ども」の部分。 |
||||
16日(火) 指導基盤 初めての専科、図工の授業。 並べて連れていく。 専科の先生曰く 「パワーがあり、おもしろい子どもたち」 同感である。 今は、まだパワーを発揮する方向性があいまいであるが、そのうち定まってくるだろう。そうなったとき、ぐんと伸びることは間違いない。 空き時間に、隣の学級の歌を指導する。 10分でかなりのことができた。 音楽朝会で歌う『さんぽ』を扱う。 一人ひとりの指導をいれていく。 これまで、一斉中心だったが、今日は、個を中心にしてみた。 結論からいうと、うーんという感じだった。 待っている間にだれてしまう子がいるのである。 一斉でやるときは、あまりないのだが… まだ、一人ひとりの指導基盤ができていないということだろう。 |
||||
15日(月) リセット 休み明けは… やはり厳しいものがある。 元に戻っている。 「リセット!」 合同音楽 音楽の先生がお休みのため私が授業。 『さんぽ』 歌う声で。 2組は、ものすごく乗ず、態度もいい。 パフォーマンス体育 体育館で授業。 私の体育は、楽しいのだがハードである。 終わるとかなり疲れる。 それだけ運動量が多い。 |
||||
| 12日(金) 最初の一週間終了 職員朝会が長引く… いつものように、さっと入れなかった。 今の段階、子どもたちは教師に100%左右される。 私の状態がそのまま子どもに反映される。 といっても、悪いわけではない。 身体測定 ・靴をそろえる ・おしゃべりをしないで待つ フラッシュカード 10マス計算 先に進みたいという氣持ちを押さえ、じっくりやっていく。 まだ、10秒切れない子がいるからである。 全員が軽く切れるようにならないといけない。 九九 ずいぶん慣れた。 毎日、2分くらいの練習。 今日は、2×6までやった。 時計 ○時、○時半、○時○分 慣れてきた。さっと答えられるようになってきた。 音読 私の音読指導は、3つから成り立っている。 ・音読 ・暗唱 ・表現読み 3つは、独立しているのではなく、絡み合っている。 冒頭の詩、そして『スイミー』を読む。 イメージ「広い海」 強弱 声のコントロール けっこう高度なことをやっている。 それができるのがすごい。 2年生でここまでできるとは… 人間の持っている能力、可能性をあたらて感じた。 歌 がらっと変わった。 もう、聴く人が驚くほどである。 響きも出てきた。 素直な分、上達が早い。 「いやだ」という子がいないことも大きい。 かなりよい。 これだけ上達が早い子どもたちは、初めてである。 書写の指導 打ち込みと止め。 まるっきりできていない子が多いので、一から指導する。 横線「一」と縦線「|」を教える。 作文 『先生について』 私について書かせる。 さあ、子どもたちはなんと書いただろう。 |
||||
11日(木) 密度 あいさつ フラッシュカード 数字を読む。+1、+2になる数をいわせる。 10マス計算 +0、+1 まだまだ。 「頭と手をつなげるのが練習」 九九 2の段 今日は、2×5まで。 2×2(ふつうは、『ににんがし』を)2人がしんがし(新河岸)といっている(笑) 時計 ○時、○時半、○時5分、10分〜50分 筆算 二桁繰り上がりのあるたし算の唱和 音読 「たんぽぽ」 いろいろな音読。 ・視線 ・表情 ・強弱(本日のメイン) 歌 歌う声で。『地球の子ども』の導入 ぐんとうまくなった。 鍵盤ハーモニカ『ミッキーマウスマーチ』強弱をつける。 バカ受け。 文章化しにくいこの実践。 ごらんになりたい方は、ぜひ新河岸小へ。 すごくおもしろいと思います。 外に出て、鉄棒あれこれ。 持久懸垂は、弱い。 それ以外に、バランス(Y字、飛行機など) カエル倒立 うさぎの足打ち などなど。 久しぶりにけ上がり、懸垂逆上がり、中抜きなどをする。 うーん、老いたり… 練習しなきゃ。 チューリップの観察 見たこと作文の導入 教室で、見てきたことを書かせる。 箇条書きで。 字がきれいな子は、少ない。 書写の指導もしなければ… 表現読み『スイミー』 「広い海のどこかに、小さな魚の兄弟たちが楽しくくらしていた」の部分。 超まじめからおふざけまで、両極の幅が広すぎるくらい広い。 午後は、午前中の復習。 学年会 打ち合わせ。 |
||||
10日(水) はやくも あいさつ、声が大きくて元氣がいい。 音読、教科書(光村図書)冒頭の文章。 さっそく、表現読みを導入する。
だらーっとした読みを修正する。 「(やってみせて)こういうのを、たれ流し読みというんです」(笑) フラッシュカード、数字を読んでいく。 今日は、一瞬しか見せない。見せたらすぐかくすようにした。 見ていない子は、答えられないようにしたのである。 動体視力のトレーニングにもなる(笑) 同様に、+1、+2をおこなう。 10マス計算…+0、+1をおこなう。 九九…かけ算の意味、2の段(2×0、2×1、2×2、2×3、2×4まで) 時計 デジタルとアナログがあることを教える。 アナログ時計の読み方がよくわからないという子が半数。 1から教える。 ・針が2本ある。長い針と短い針。 ・短い針を見る。 「短い針だけを見ればいいんです」 「(短い針5を指す)何時ですか?」 というようにやっていく。 午前と午後を教える。 AMとPMも教えてしまう。 「今何時ですか?」 「9時」 「今は、午前中だから、『午前9時』と答えましょう」 昨日やった「限定」をここでも教える。 私の体験を話す。 「9時に、丸井の前ね」 仲間から連絡がきた。 5人集まった。 しかし、あと1人こない。 どうしたのだろうか… 約束を破る男ではないのだが… あとで電話すると(もう20数年前のこと、携帯電話はまだ生まれていない) 「いったよ。丸井の前に」 「じゃあ、どうして会わなかったのかな。正面口でしょ」 「そう、正面口。暗くてよく見えなかったのかな」 「暗いって、午後9時にいったの?」 「会合にしちゃ、遅い時間にやるなーって思ったんだ」 「午前9時だよ」 ちゃんちゃん。 自分が思っていること、他人が思っていることは違うのである。 電話連絡をするとき、『午前9時』といえばよかったのである。 こんな感じでやっていく。 なれてきたら、○時半を扱う。 筆算 1年生のころつかっていたノートを見せてもらう。 筆算をやっていたので、すぐに入る。 + − 位取りを間違えないように、線を引かせる。 | | | 赤、青など、黒以外の色。 25 繰り上がりの「1」を下に書かせる。 +25 (今や、常識か) ―1―― 50 私のあとについていわせる(唱和)。 「一の位から計算します。5と5で10。一の位に『0』を書きます〜」 というように。 35 +35 ―1―― 60 45+45、テストとして、18+14をやらせる。 ミスした子もいた。 ・答えはあっているが、繰り上がりの「1」を書き忘れた。 ・十の位の答えを、5と書いた(繰り上がりの「1」をたしていない。 ・計算ミス 今日は初日。 毎日やっていれば、少しずつ覚えていくだろう。 『丸、点、かぎ』 ・うんちが出たよ 「出たのは何ですか」 ・ここではきものをぬぐ 「脱いだのは何ですか」 読み聴かせ『スイミー』 指名なし発言。一人最低一言、感想をいわせる。 時間はかかったが、何とか全員発言。 漢字…1年生の復習。 書き順、意味、波及 「九」の書き順を扱う。 間違っている子が3分の2以上。 ノから書くことを教える。 ついでに「丸」を教える。 「先生、『円』の『まるい』とどう違うの?」(Oくん) 素晴らしいつっこみをほめる。 「まるいには、『丸い』と『円い』があるんです。どう違うんでしょうね」 ここでは、わざと教えない。 すぐ教えること、すぐ教えないことを、はっきりわけて指導している。 今日のメインは、漢字たし算 木+木=林 など、いくつか例を挙げる。 子どもたちは、どんどん見つけた。 木+木+木=森 口+玉=国 木+交=校 竹+立=笠 田+力=男 夕+夕=多 日+十=早 一+一=二 一+二=三 夕+口=名 一+白=百 火+火=炎 日+月=明 日+立=音 日+青=晴 金+令=鈴 田+土=里 口+口=回 木+公=松 二+人=天 木+一=本 日+一=目 などなど、たくさん出された。 |
||||
9日(火) 本格的にスタート 今日から授業を本格的にスタートする。 授業=学級創りである。 まずは、あいさつから。 姿勢を正しくさせる。背もたれにもたれない。足の裏をぴたっとつけるなど。 椅子の調整。 音無でさっと立てるか、さっと腰掛けられるか、できる位置を考えさせる。 つまり、椅子を動かさないで立つ、腰掛けるということである。 決まったところで、手で(立つように)合図。 「おはようございます」 元氣な声である。 低学年特有の語尾上がりもなし。 まずは、よし。 「先生、席替えは?」 の声をかわし、次に進む。 フラッシュカード 0〜9を書いたカード まず「0」を見せる。 「一緒に、読んでみよう」 「0」 声がそろうまで、数回かかった。 「1」 「2」 「3」 ここで、「8」を出す。 「4」 反応様々。 ・間違えなかった ・間違えちゃった ・… 「今『4』といった人、とてもいいです」 「1、2、3ときたから、次は『4』と予想したんですね」 「予想は、とっても大切なことです」 たとえを2つあげる。 ・「プップー(クラクションの音)となったら、誰かおならしてる(笑)」 「そうじゃないね。車がくるなって思うでしょう」 など。 一通りやる。何度もやる。 大きな声でそろうまで繰り返す。 これは、大事なことである。 わかる人にはわかるのだが… 次は、+1である。 「+1になる数をいいましょう」 たとえば「2」だったら「3」と答える。 +2になると、声がバラバラ。 急にそろわなくなった。 「いいんですよ、今はできなくても」 「+1は、簡単だったでしょう」 「練習すれば、+2も簡単になります」 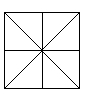 漢字、前日の続きをおこなう。 例の図である。 この中から漢字を探す。 20個見つけたら2年生として合格 さて、昨日の続きである。 結果からいうと、なんと60以上も見つけた。 すごい! あきることなく、探していた。 ここで教えたこと ・できるだけ自分の力でやる ・できないときは、友だちや先生に聴く ・できないときは、調べる。 ※ここで教科書を使わせる。 学習法の導入である。 途中、総合的に学習を進める。 「水」が出たところで、ヒントを出す。 「水に似ています。夏、暑いときにこうやって…」 「かき氷」 「そのこおり」寒い 「いえ、その通り」 「氷という字を教える」 「習ってないもん」 という子がいる。 決まり文句である。 習ったのに読めない、書けないことがあるだろう。 それにはふれない。 「うちのクラスでは、『習っていないもん』といってはいけません。『今、覚えよう』です」 一つ出たら、関連するものをいわせるのである。 意見の出し方の基本形を示唆したのである。 「氷は、『こおり』か『こうり』か」 意見がわかれた。 「お」だという子が、3分の2。 正解である。 第二弾 「○○通りの『通り』は『とおり』か『とうり』か」 今度は「う」の子が3分の2以上。 いやはやおもしろい。 その他、(違う漢字で)書き順も扱う。 声のコントロール 音読させる。 地声でだらっと読む子どもたち。 リズムもテンポもない。 私がやってみせる。 「先生のように読みましょう」 百聞は一見にしかず まねさせるのがいい。今の段階では。 すぐによくなった。 しかし、地声は変わらず。 地声とそうでない声の説明。 実際にやってみせる(爆笑) 「さあ、やってみよう。ぼく、やってみるという人」 最初に手を挙げた子をほめる。 「みんなが手を挙げないとき、最初にやる…とっても勇氣がいるんです」 「えらいぞ!」 どんどん手が挙がる。 思ったよりもよくできる。 「やりたくない人」 3分の1の子の手が挙がった。 予想通り。 音読の声を教える。 実際に読ませる。 できる子もいれば、できない子もいる。 当然である。 今日は、実態把握で終わり。 続いて歌。 校歌を歌ってもらう。 地声である。 歌う声を教える。 すぐにできた子は5人。 声質もいいし素質がある。 変わらない子も多い。 これまた当然である。 実態把握で終わり。 暫定の席決め。 好きなところに座らせる。 10マス計算の導入。 今日は、0と1である。 やり方を教える。 0は簡単にできた。 大掃除 |
||||
8日(月) 出会い 始業式 出会い。 不思議そうな顔をして私を見ている子どもたち。 反応はいろいろ。 おもしろそうである。 1年生歓迎の練習。 昨年度受け持っていた先生にお願いする。 1回通してもらう。 実態がわかったところで指導。 詩の暗唱、リズムとテンポについて、声を下げないことを指導する。 ぐんとよくなった。 ※本番では、元に戻っていた(笑) そう甘くない。 待ち時間が、1時間近くあった。 校庭で遊ばせてから、漢字クイズ。 これは、熱中した。 「2年生は、20個見つけよう」 みんなでやって10個見つけたところでストップ。 あとは、明日やることを告げる。 「先生、これって宿題」 「宿題いやだ」 「やってこよう」 はやくも、ジャブのつきあいである。 子どもは、この先生はどこまで押せるか試している。 押せないんだねーこれが(笑) その他、やったこと。 あいさつ、立ち方、すわりかた、歩き方。 |
||||
4月5日(金) 前日 前日出勤。 教室移動。6年生が手伝いにきてくれた。 よく働く子がいる。Sくん。さすが6年生。 感心した。 入学式の準備。いろいろ。 1年生の教室で、教科書、グッズの用意、確認。 体育館で会場準備。 「歓迎の言葉」の練習をしていた。 6年生の動きを見る。 実態がよーくわかった。 私の担当する○年生はどうだろうか。 午後は、教室の整理、押印。 保健、給食関係などなど、子どもの名簿をつくっていく。 押印しながら、その子を思い浮かべる。 そして、名前を覚える。 名前から、その子をイメージする。 どれくらい当たっているだろうか。 当日が楽しみである。 学年会で打ち合わせ。 職場に活氣あり。 みんなはりきっている。 いいことだ。 |
||||
| 4月1日〜4日 学級創りの構想。 ここ数年、同じ学年が続いていた。 6,6、6 オーメンである(笑) 久しぶりの○年生。※8日まで公開できない。 5回目の○年生。 大好きな学年である。 やりやすく、ものすごく力が伸びる学年である。 たとえ力はついていなくとも、回復は早い。 6年生だと、1〜5年までやらなければならない。 つまり、1年で6年分である。 かなりつらいものがある。 ○年生だと○年で済む。 実にありがたい。 余裕がある。ありすぎる。 杉渕流の実践が一番できる学年である。 わくわくしている。 ○年生を受け持ったのが9年前。 当時に比べ、力量はアップしている。 どれくらいのことができるか、すごく楽しみである。 |