| プラスにいくか、マイナスにいくかの分岐点があります。 ターニングポイントです。 ボーダーラインは、もう少し幅があります。 例えば、選挙です。 雨が降ると…「行こうかな…やめようかな」 悩む人がいます。 この場合、友だちが 「一緒に行こう」 といえば行くでしょう。 「行かなくていいよ」 といわれれば行きません。 このようなことは、たくさんあると思います。 迷いの幅、これがボーダーラインです。 学級創りも同様です。 毎日、「ボーダーライン」があらわれます。
勝負の分かれ目です。 多くの場合、教師がキーマンです。 教師の一言によって、プラスにもマイナスにもなるのです。 |
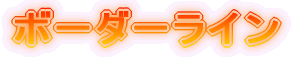 掃除の時間、私は一人で教室掃除をします。 ときどき、出張当番の掃除個所を見て回ります。 きちんとやっている班もあれば、そうでない班もあります。 誰かがしゃべり始めると、 つられてしゃべり 氣づいたときは総崩れ というのが、おきまりのパターンですね。 逆もあります。 展覧会のかたづけのときのことです。 だいたいの仕事が終わり、全体がだれ始めたとき、 Sくんがいったのです。 「よし、だいたい終わったから他の学年を手伝おう」 この一言で、雰囲氣が一変。 子どもたちは、パッと散りました。 手伝いにいきました。 「もういいよ。休み時間だから」 「いえ、やります」 誰も休もうとはしません。 うれしく思いました。 みんなでかたづけを済ませました。 この違いは、どこからくるのでしょうか? 運命の分かれ道 というものがあります。 岐路に立ちます。 境界線です。 どっちを進むかで、180度違ってきます。 決断の時です。 大げさないい方かもしれませんが、毎日岐路に立つのです。 私たち(教師と子ども)は。 これを「ボーダーライン」と呼んでいます。 勝負所ですね。 Sくんの一言で、ベクトルが、がんばる方に向きました。 ちょとしたことで、結果は驚くほど違ってきます。 総崩れになるか、ちゃんとやるか… ボーダーラインを意識できるか? ベクトルをプラスに向けるちょっとしたことができるか? 考えさせられました。 |
| ボーダーライン 2 今、漢字カルタをやっています。 「漢字カルタ」「部首カルタ」の2種類です。 2週間やりました。 子どもたちはものすごく速くなりました。 もう勝てませんね。 年のせいか反射神経が鈍っています。 体が反応しないのです。 私が入ると、異常に燃えます。 もうやらない(笑) 閑話休題 自分たちで、カルタをつくろうということになりました。 中学校に持っていこうというのです。 まあ、嫁入り道具のようなものですね(笑) それから、他の学年にもつくってあげよう ということになりました。 楽しさのお裾分けでしょうか。 卒業制作の一つとして、「漢字カルタ」をつくることになりました。 まずは、1年生の分をつくりました。 2日間、あわせて2時間くらいでしょうか。 とてもいいカルタができあがりました。 (※カルタの秘密については、いずれ) さっそく、1年生を招待しました。 仲良し学年集会のときに、一緒にやったのです。 最初は、6年生が見本を見せました。 4人一組で対戦します。 1年生の漢字55枚をとります。 10枚くらいとったところでやめました。 次は、1年生。 6年生が一人ひとりにつきます。 「あそこにあるよ」 「『川』だよ」 いいすぎるくらいヒントをいっています。 自分がとって1年生に渡している子もいます。 2回目 「あまり口出ししないように」 といいました。 できそうな感じがしたのです。 「どうしてもわからないときだけ、教えてあげなさい」 1年生は真剣そのもの。 とるのも速いです。 予想より、ずっとずっと速いです。 すごいと思いました。 6年生も、びっくりしていました。 1年生は真剣でした。 カルタをもらって、大喜びしてくれました。 それを見た6年生も、大喜びしていました。 「先生、大変だったけどつくってよかった」 「今度は、2年生の分をつくろうよ」 さっそく、つくりはじめていました。 すべてタイミングがよかったです。 ・漢字カルタの導入のタイミング ・自分たちでつくる(2週間したところで) ・卒業制作とする。 ・1年生と一緒にやる。 ・1年生にプレゼントする。 |
| ボーダーライン 3 今、漢字カルタをやっています。 ブレイクしています。 漢字が苦手な子も、意欲的です。 卒業制作で、漢字カルタをつくっています。 (他学年にあげるのです) つくるたびに、うまくなりますね。 漢字の部分は、毛筆です。 書写の練習にもなっています。 さて、今回は1年生と対戦しました。 1年生vs6年生 です。 1グループ、1年生4人に対し6年生1人。 6グループあります。 6年生は、読み終えるまでとってはいけない というルールにしました。 やる前に、1年生を集めました。 作戦を授けました。 (秘密) 4対1 きついルール。 私によるアドバイス。 どうなるでしょうか。 白熱したバトル 大活躍の1年生 苦戦する6年生 対戦成績は、3勝3敗でした。 「3勝3敗、引き分けです」 「引き分けの場合は…」 「…」 「1年生の勝ちとします」 大歓声。 大喜びの1年生。 1年生、すごく速くなりました。 うんとほめました。 1年生の先生に、話を聴きました。 すごく喜んだそうです。 すごく自信を持ったそうです。 |
| ボーダーライン 4 学習のシステム 「四字熟語カルタ」をつくっています。 現在、70枚になりました。 毎日、5枚ずつ増やしています。 各班で、1枚ずつつくります。 例えば、「一騎当千」という札をつくるとしましょう。 表には「当千」と書きます(筆で書きます)。 裏には「一騎当千」と書き、ふりがなをふります。 役割を分担します。 ・「当千」と筆で書く ・「一騎当千」と書き、ふりがなをふる ・辞書で意味を調べる。→みんなに発表します。 これらを4人で分担します。 5枚同じ札をつくります。 できたら、他の班に配ります。 私の学級、生活班は5つあります。 このようにして、毎日5枚ずつ札が増えていくのです。 最近は、3分でつくります。 かなりのスピードです。 四字熟語カルタを2回戦、そしてカルタづくり。 合わせて、10分かかりません。 これを、毎日行うのです。 遊んでいるうちに、だいぶ覚えましたね。 私も(笑) |
| |