 鮮度が命 新学期。 学級創りは、最初の1週間が勝負です。 この期間を「黄金の期間」といいます。 黄金の期間。 子どもも教師も新鮮です。 私の学校も活氣に満ちています。 エネルギーがあふれています。 その新鮮さがあるうちが勝負です。 鮮度の保障は、3日間。 賞味期限は、1週間。 このときだけの、限定セールです。 何をするか、重要な問題ですね。 ★黄金の期間 初日 始業式。 3年連続の6年担任。 代表の言葉 3人。 昨日指導したのだが… グンとよくなっていた。 彼らなりに考えている。工夫している。 入学式準備のため、学級指導は15分。 まずは、あいさつから。 「おはようございます」 元氣がいい。 次の段階へ進む。 さっと立ってあいさつすることを教える。 あいさつのとき、イスは入れない。そのまま。 立った瞬間にあいさつする。 1回だけやってみせる。 手で立つように合図する。 「おはようございます」 さっそく教科書(国語と算数)を配り、授業をする。 国語…音読 扉の詩を扱う。 まずは、読ませてみる。 全員が教科書から目が離れない。 「だれに聴かせているの?」 聴き手を意識させる。 下を向いて読む(教科書から目を離さない) →聴き手意識が薄い。 だれに聴かせるのか→たとえば、1年生。 目を見る。目で伝えることを教える。 ペアで練習。 相手に語りかけるように読む。 まだまだうまくできないが… 算数…『分数のかけ算』 やり方を指導する。 唱和という方法を教える。 算数上達法を教える。 →定規を使う。 →唱和する。 聴き手をつくる。ぬいぐるみ、犬、猫など。 声を出す。→耳から入れる。 入学式 式中の態度は… 子どもによってさまざま。 かたづけ 入学式後のかたづけ 役割分担してやるか、みんなでやるか この場合、どちらがいいか。 話し合わせる(1年生記念撮影 かたづけを待っている間に) 「1年生とお母さん方が退場してからかたづけます」 撮影中にかたづけようとした子に対して。 終わったら、遊ぶのではなく 自分で、自分から仕事を見つける。→意識 学級指導 心のスピード、頭のスピード いくらでも速くなる。 イニシアチブ 自分から働きかける。 自ら進んで活動する。 ひとのため、みんなのため 上級生の行動は いい行動…1000やって1伝わる。 悪い行動…1やると1000伝わる。 見えなくても伝わる。 体の中にはセンサーがある。 感じる。 たとえ、意識していなくても。 宇宙の法則 やったことが自分にかえってくる。 今何が大切か 手いたずらしているSくんに対して。 「先生の話」 しかし、行動はそうなっていない。 具体的に示すこと。 そう思っていても伝わらない。 ◆認識 活動の意味を教える。 これをやることが、どういう意味をもつのか。 これをやることで、だれの役に立つのか。 1ついいことをすれば、確実によくなる。 たとえば、ごみ拾い。 1つ拾えば、確実に一つごみは減る。 |
| ☆黄金の期間 2日目 学級創り2日目 早い子は、7時40分ころ登校。 一緒に学校を掃除する。 私は、いつものように2階の廊下を掃除する。 登校した子どもたちは、思い思いの行動。 1年生の教室をきれいにする子 1階の廊下を掃く子 下級生に声をかけ、一緒に机を拭く子 花の水やりをする子 さまざまである。 昨日語った「イニシアチブ」 さっそく実行しているのがうれしい。 職員朝会後、教室へ。 昨日に入れたことができるか。 「いいかい」 さっと立ってあいさつ。 覚えていた。 「おはようございます」 張りのある声であいさつ。 バッチリできた。 続けて一人ずつのあいさつ。 「おはようございます」 声についての説明をする。 やる氣は目に出る 声に出る。 あいさつとは、エネルギーの交流。 相手にエネルギーを送ること 相手からエネルギーをもらうこと 言葉にエネルギーを乗せる。 声が大きいというのはやる氣があるということ。 だから、先生方は声を大きくというのだということ。 順番は自由。 だれが出るか。 予想通りのこが出た。 ずっと男子が続く。 男子、だいたいオーケー。 けっこう声が出ている。 間があいたとき 「『早くいわないかな』と思っている人がいるでしょう」 「こういうときは、予想するんです」 「次は、だれがいうか。よく見るとわかりますよ」 「この、『予想する』ということは何にでも役立ちます」 続けて女子。 女子は、声が小さい。 まだまだ、これからである。 しかし、早くも化けた子がいた。 「化けた」とは、大きく変わったという意味。 殻を破り新しい自分を創ったという意味。 1日で変わる… 変化は急激に訪れる… あいさつの次は、音読。 昨日の続きである。 一まいの紙から 船が生まれる 飛行機が生まれる 一回読ませる。 「昨日いわれたことを意識した人」 約半数が挙手。うれしそう。 半数の子は、しまったという表情。 「もう一度やってみます」 ずいぶんとよくなった。 意識するかしないか 大きな違いである。 指導する。 5年生のときにくらべ、声が出てきた。 重たくなくなってきた。 言葉がはっきりしてきた。 昨日一日でかなり上達している。 伸びるときは一氣に伸ばす 声を上に持っていくこと 声を腹筋で支えること を教える。 いい感じである。 声が響くようになってきた。 聴き手を意識させる。 「君たちの前に誰がいますか」 「何人くらいいますか」 「人数によって、目の使い方が違ってきます」 「今度は、目の前に一年生がいるとイメージしましょう」 「一年生に語りかけるように読んでみましょう」 一人ずつ読ませる。 化けた子の表情がいい。 今までにない表情。 確実に変わった! 読み方を指導する。 「一まい」について、教える。 「『一まい』と読む前に、心の中で読むんです」 「たとえば、心の中で『たった』と読みます」 「そして、声を出して『一まいの紙から』って読むんです」 「やってみましょう」 読み方が変わった。 先ほどは、「一まい」ではなく「ちまい」と聴こえた。 今回は、全員「一まい」と聴こえた。 わずかな指導で、がらっと変わる。 次回の予告 「この紙は、どんな紙でしょう」 「この紙のことを大切に思っているのでしょうか」 などなど。 ヒントを出す。 あいさつ→音読→歌 表現の指導 歌の指導を始める。 5年生の3学期くらいから、声が出てきている。 まさに昇り調子。 どれくらい歌えるか実力を見せてもらう。 一人ずつ歌わせる。 ロングトーン 「あー」 順番にやらせる。 いい子をほめる。 「これは伸びるという子には、何回もやります」 普通は逆である。 私の場合、伸びそうな子を何度も指導する。 wくんは、見る間に変わっていく。 「口は、もっとたてに開けてごらん」 「そうそう」 「自分から、声のレーザー光線が出ている」 「黒板に声を当ててごらん」 「いいぞ」 「次は、『元氣玉』知ってる?」 多くのこが知っていた。 「声で『元氣玉』をつくるんです」 「教室いっぱいの玉をつくるんです」 こんな感じで指導していく。 wくんは、ぐんとうまくなった。 『ともだち』の一部分を歌わせる。 「ともだちさー」 男子は、まあまあ。 女子も前よりはずっとよい。 すごく積極的になってきた子がいる。 声も出している。 けっこういい。 いけそうである。 ネーム貼り 机、イス、ロッカー、壁掛け、靴箱、傘立てにネームシールを貼らせる。 ※ビニールテープを切ったもの 机とイス、ロッカーをきれいにさせる。 長年の蓄積? ごみが出る出る 脚の裏は特に汚れている。 細かい部分は、歯ブラシ(使用済みの)できれいにする。 「机がきたなくて勉強ができるようになった人は一人もいません」 「イチロー選手を知っているでしょう〜」 話をする。ゲーム後、グローブとスパイクを磨いてからバスに乗る。 さすがに一流選手は違う。 算数の授業 ノートの使い方がメイン。 昨年度の交流授業が効いている。 指示がどんどん入っていく。 書き方、色の使い方、スペースの開け方などを指導。 『分数のかけ算』も教える。 学習の方法を教える。 1 まず、自分でやってみる。→先生に聴く。 2 先生に少し教わってやってみる。ヒントをもらう。 3 先生と一緒にやってみる。 「できない」「わからない」 という前に上のことを考えるようにいう。 そうすれば、こういう言葉は出ない。 「2と3の人、先生に聴きにきなさい」 真分数×真分数 ◆応用 帯分数×真分数 真分数×帯分数 ◆応用2 真分数×整数 整数×真分数 このようにステップを踏んでいく。 「できない」「わからない」 すぐ先生にいうように。 できるまで教える。 わかるまで教える ことを話す。 変形(形を変える) 自分が得意な形に変えることを教える。 コメント…感想、わかったことなど を書かせる。 大掃除 先生に対する要求 算数をできるようにしてほしいという子が多かった。 |
| ★黄金の期間 3日目 イニシアチブ 子どもたちと一緒に、学校をきれいにする。 朝会。 私は、歌の指導を担当している。 今日は、校歌。 2人の子を指名。5年生と6年生。 見本をやってもらう。 校歌の一節である。 「はまゆう花咲く白砂ふんで」 1人でやっても、かなり声が出る。 どよめきが起きる。 全員で歌わせる。 「はまゆう花咲く白砂ふんで」 休み明け。声が出ない。口も開いていない。 一つひとつ指導していく。 口の開け方「指が2本はいりますか」 実際にやらせる。 少し声が出てきた。 何回かやる。 2人にやってもらう。 次は、がくねんごとである。 2年生から順番にやらせる。 今日は、5年生の声がよく出ていた。 そして、6年生。 杉渕学級(単級)の番である。 今までにない声量。 5年生よりずっとボリュームがある。 最上級生の自覚か? 次元が違う。 「6年生、急にうまくなったね。びっくりした」 と教頭先生。 子どもたちもびっくり。 「いつもと違う!」 6年生の子どもたちも、びっくりしていた。 私もびっくりした。 基礎の時間 あいさつ3日目。 「いいですか」 さっと立って 「おはようございます」 はりのあるこえが。 一発でオーケー。 すぐ、音読に入る。 斉読。 声が大きい。 よく響いている。 声の重たさがなくなりつつある。 もう少し上げるように指示。 「船が生まれる」(教科書の扉の教材)を扱う。 意識して読まないと、読み方が変わらない。 意識して読んでも、読み方が変わらない。 表現は、難しい。 まずは、3通り、次は10通りの読み方ができるといい。 たとえば、 ほんの少し楽しい 少し楽しい 楽しい とても楽しい すごく楽しい 5通りの読み方をさせる。 3人。 まだ、強弱のみの表現。 音読で大切なことは何か? 考えさせる。 1人ずついわせる。 イメージ 楽しかったことを思い出していう。→感覚の再現 いい方を変える 声の大きさの変化 強弱 表情 氣持ち など、いろいろな考えが出された。 次回は、つっこんで聴いていきたい。 たとえば「氣持ち」。 氣持ちを表すには、どうするか? 『ビリーブ』(歌)の導入 以前から、取り上げたかった歌。 今年度の子たちのためにとっておいた歌である。 視写させる。 音読させる。 声は大きい。 しかし… 詩にならない。 ただ読んでいるだけである。 読み方を考えさせる。 やらせる。 S君が、いい感じ。 見本をやってもらう。 他の子は、まだまだ。 今までに染みついたことは、なかなか抜けない。 今は、意識するだけでいい。 イスに洗濯ばさみ(2つ)をつける。 そこに、ミニぞうきんをつける。 算数の授業。 今日初めて登校した子のために、もう一度やる。 昨日の復習である。 『分数のかけ算』 指導主事の先生方が参観。 唱和。 忘れた子に対して。 「忘れたら、また覚えればいいんです」 真分数×真分数 帯分数×真分数 真分数×帯分数 整数×真分数 真分数×整数 このようにやっていく。 ポイントを書かせる。 『ビリーブ』 今度は歌。 歌を1回聴かせる。 「それでは、歌ってもらいます」 1回で覚える。 大切なことである。 意識と行動。 1人ずつ歌わせる。 もちろん、冒頭の部分だけである。 パスも認める。 歌えない子多し。 やった子をほめる。 W君がいい。 昨日の布石が効いている。 音程もしっかりしている。 すぐに覚えた。 「君には才能がある!」 R君がいい。 この歌を知っているそうである。 音程も取れている。 「もう一度聴かせます」 2回目、聴かせる。 聴く意識が違う。 覚えようという顔である。 「パスした子も、やってもらいます」 ※パスは2回まで認めている。 「先生、2人でやってもいい」 女の子2人がいいにくる。 この考えを取り上げる。 「できませんといわないで、なんとかやろうとしています」 「一人ではできない→でも、2人ならできる と考えました」 あきらめないで方法を考えたのがいいとほめる。 ほとんどの子が歌った。 3回目 音程がそろってきた。 4回目 不安定な部分を聴くように指示。 ぐんとよくなった。 これは、「覚え方」の学習であることを教える。 覚え方。 ポイント 1回1回、ポイントを決めて覚える。 そして、意識して練習する。 かなりよくなったので、次の段階へ。 曲想の指導をする。 プラスαの行動について語る。 いろいろな例を出す。 どっちに行くか 社会の授業 学習方法を教える。 豊臣秀吉のビデオを見せる。 歴史学習の導入である。 秀吉の行動 草履取りの話し。 先ほどの、「プラスα」とつなげる。 給食準備 前年度のようにやらせる。 様子を見る。 いい点とよくない点がある。 一長一短である。 ごちそうさまは、早い。 基礎 今日一日の復習をさせる。 音読、歌、算数というように順にやっていく。 |
| ★黄金の期間 4日目 朝 頼まれて、授業。 音読『ふきのとう』表現読み。 さっそく指導。 イメージさせる。 「さむかったね」 一人ひとりやらせる。 個別指導。 一人二役 やってみせる。 お得意のパフォーマンス。 ちょっとやり過ぎた(笑) 基礎の時間 新採の先生が参観。 表現読み。 1人ひとりやらせる。 「船が生まれる」 だいぶうまくなった。 声が上に行くようになった。 『ビリーブ』 表現読み 1人ずつ読ませる。 これまた、ずいぶんうまくなった。 わずか1日、されど1日。 うまくなるのに期間は関係ない? 歌 発声練習 ロングトーン 声を当てる 響かせる などなど。 算数 ホームワーク(家庭学習)で、よくわからないと書いてきた子がいる。 その問題を取り上げる。 8 12×ー 15 できた子には、この問題のポイントを予想させる。 ポイントは、約分である。 1 答えを出してから約分する。 2 計算の途中で約分する。 どちらがやりやすいか、わかりやすいか聴いてみた。 半々だった。 両方できるといいことを教える。 「時と場合によって使い分けてみましょう」 漢字カルタの導入。 彼らにとって初めての経験。 えらく盛り上がった。 続けて、リーグ戦を導入する。 10マス計算、実態調査。 うーん、スピード不足。 「1年生レベルの問題です。でも、速くやるとなると…難しいでしょう」 「考える」ノートの導入 結果の分析。 分類させる。 1 できた 3〜6秒 2 まあまあ 7〜9秒 3 できない 10秒以上 練習方法を考える。 「どうしたら速くなるか」 ヒントを出す。 スピードとは ・心のスピード ・頭のスピード ・ハンドスピード 絵の導入 5年生のとき、5分間スケッチをやっていた彼ら。 どれくらい描けるか様子を見る。 題材は自由。 ところどころ、アドバイスする。 上手な子多し 放課後残ってやっていた。 基礎 表現読み 歌 階段でやる(場所を変える)。 響きを体感させる。 音読もやってみたい。 算数の復習など。 |
| ★黄金の期間 5日目 漢字の授業 ・漢字プリント 2年生レベル。 ・基礎知識を教える。 部首、似ている字 未と末など 班対抗で、木偏の字を見つけるゲーム。 委員会の担当を決める。 人氣ある委員会、そうでない委員会はっきりとわかれた。 「みんなのために活動するのが委員会ですよ」 立候補が多い委員会は、くじ引き…ではなく、「あっち向いてホイ」で決 める。 給食のとき、委員会ごとに集まる。 ミーティング。 委員長、副委員長、書記を決めさせる。 第一回委員会に向けて準備開始。 音楽の授業 今日は、私が授業をする。。 新採の先生(音楽)に見ていただく。 リコーダー 基礎の指導、タンギング、息の吹きこみ方、姿勢など。 パフォーマンス。救急車(シーソー、シーソー)による強弱の指導。 歌 『翼をください』曲想 『君をのせて』曲想 基本から高度なことまで扱う。 体育 初めての体育。 実態を調べる。 柔軟性、体力等々。 「SOHRAN」の導入。 1年生の給食準備手伝い、7人と私 7人は、1年生と給食を食べる。 基礎 算数ノート、今まで学んだことを使って書く。 |
| ★黄金の期間 6日目 1日授業参観・保護者会 朝 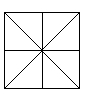 この中から漢字を探しましょう。 君はいくつ見つけられるかな。 定番の問題。 けっこうおもしろい。 「今までの最高は107個です」 熱中する子どもたち。 2、3校時は図工。 子どもたちを送っていく。 「お願いします」 といって帰る。 いろいろな学級の授業を参観する。 4校時 基礎の時間 10マス計算(たし算) 0〜9まで、一つずつやる。 制限時間は、10秒である。 練習法、上達法を教える。 音読 「一まいの紙から」 本日のメイン。 基本…立ち方、姿勢、教科書の持ち方、腹式呼吸など 発声…声の出し方、支える、コントロール 強弱、広げる、響かせる イメージ…視線、イメージの表現、聴き手意識など 子どもたちの音読、時間がたつにつれどんどん変わっていった。 ものすごく上達した(まだ、仮の上達、身についたわけでない)。 それだけ、可能性がある! 漢字探し(先ほどの続き) 実に熱心に探していた。 熱中。 一番見つけた子は、71個。 参観していた校長先生は、50個? 休み時間、放課後もやっている子がいた。 M子さんは、101個見つけた。 「先生、漢字辞典貸してください。家でも、調べてきます」 やる氣十分。 歌 発声練習…『ゆかいに歩けば』の一部分。 『ビリーブ』 5校時 国語と算数 1年生給食準備手伝いがあるため25分間の授業。 算数…『分数のわり算』 やり方を教える。 唱和。 ノートに書かせる。 例題をやる。 国語…考える力 題材、これまた定番の「黒い目のきれいな女の子」 6校時 本日の復習 保護者会 |