| 時間を見直す 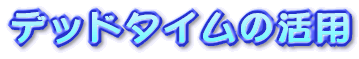 先日、ある学級を参観しました。 給食準備の時間、班対抗でクイズをしていました。 「早押しピンポン」です。 ウルトラクイズ(古いかな)のイメージです。 各班(給食当番以外)から、一人ずつ出てきます。 先生が問題を出します。 早く押した子のランプがつきます。 問題は、いろいろありました。 項目によって色分けされていました。 ・百人一首…上の句を聴き、作者をあてます。 ・ことわざ…(例)「せいては」を聴いたら「ことをしそんじる」 と答えます。 ・歴史 ・元素記号 ・都道府県の県庁所在地 ・名言 ・四字熟語 などなど。 見ていて、おもしろかったです。 子どもたちは、よく覚えています。 給食中も、クイズのカードを持っていって覚えていました。 今は、自分たちで問題をつくっているそうです。 自分でつくった問題が多いと有利ですからね。 全員、クイズに正解した班からいただきますができるのです。 トップとラストの班、差は2分くらいです。 見事なシステムです。 遊びながら、いろいろなことを覚えられます。 子どもたちのやる氣を引き出します。 違う切り込み方をしてみましょう。 それは、「デッドタイム」(死んだ時間)の活用です。 給食準備の時間、10〜15分くらいあると思います。 何もしない学級と、この学級では… 1年たったら、ものすごく差がつくでしょうね。 みなさんは、給食の待ち時間をどう活用していますか。 私の学級では、全員で準備をします。 ・給食当番 ・花の水かえ ・ロッカーの整理 ・かたづけ ・ノート配り ・プリント配り ・係の仕事 ・その他いろいろ だいたい、7分くらいで終わります。 次は、給食後です。 10分間を使います。 食べるのが早い6年生だから使える技かもしれません。 クイズを5分間やります。 歴史クイズ、ことわざクイズ、四字熟語クイズが多いですね。 一人一問、出題します。 5分たったら終了。 明日は、そこからスタートします。 「デッドタイム」の活用とは、一石二鳥の発想です。 朝会の後 教室に戻るまで 体育館で朝会が行われます。 子どもたちは、教室に戻ります。 この間に、何かをやらせていますか。 たいていの場合、何もしていないと思います。 この時間がデッドタイムです。 先日、朝会で鼓笛の練習をしました。 その後のことです。 私は、次のようにいいました。 「教室まで、演奏していきなさい」 笛を吹きながら教室に戻るのです。 このように、1日を細かく見ていくと「デッドタイム」が見つかります。 いかに時間を無駄に使っているかがわかります。 |
| 何に着眼するか これが問題です。 生活をきちんとするためには、朝、昼、帰りの3つ(はじめ、なか、終わり)の活動を見直す必要があります。 時間帯に目をつけましょう。 朝 1日の始まりです。「今日もやるぞ」という心構えをつくる。心と体のウオーミングアップをさせたいものです。 学習の構えができていないうちに授業にはいると、うまくいきません。 「はじめよければ終わりよし」です。 1 朝きてから、朝の会までどうするか 2 朝の会をどうするか 先生がくるまで騒いでいる…という学級が多いようです。 昼 なかです。これは、給食と掃除と考えていいでしょう。 給食 3 給食準備をどうするか 4 給食中をどうするか 5 給食かたづけをどうするか 掃除 帰り 6 帰りのしたく 7 帰りの会 これらの子とがきちんとすると、生活のリズムができてきます。 学級全体がシャンとしてきます。 今まであまり意識していなかった点を意識してみましょう。 具体例 杉渕学級の例 朝 朝自習 イニシアチブ…掃除、整理整頓、下級生を教える 漢字プリント 昼 給食準備…手の空いている子は、教室整理、花の水かえなど 給食後…歴史クイズ、リコーダー、今日のまとめ、イニシアチブなど 帰り ・今日のまとめ ・リコーダー ・歌 ・表現読み ・太鼓の練習など |
アクセスタイム 育っていない学級を見ると、無駄が多いですね。 なかなか授業が始まりません。 取りかかりに時間がかかるのです。 ※取りかかりにかかる時間を、アスセスタイムといいます。 ある学級を見てみましょう。 国語の授業のはじめです。 教科書、ノートを出している子はいません。 「国語の勉強を始めます。日直さん、号令をお願いします」 「…」 「だれですか、今日の日直は?」 あいさつが終わったと思ったら、お説教。 「どうして、教科書とノートを出していないの」 「早く、出しなさい」 さっと出す子はいない。 おしゃべりをしながら出す子がいます。 出そうとしない子もいます。 ロッカーに教科書をとりにいく子もいます。 ここまでで、5分。 あとは、おして知るべしでしょう。 無駄のオンパレードでした。 もう一つの学級を見てみましょう。 チャイムが鳴りました。 「はじめよう」 だれからともなく、声が。 教科書、ノートはすでに机上にあります。 教科書は、開いてあります。 子どもたちは、音読を始めました。 教師がきました。 子どもたちは、音読を続けています。 スタートで、こんなに差があるのです。 わずか1時間の授業で。 1年たったら、どれくらい差がつくでしょうか。 |
一石○鳥 たくさんのことをしなければいけない現実があります。 国語は国語、算数は算数、別個に考えていくと沈没してしまいます。 いっぺんに、いろいろな力をつけましょう。 たとえば、10マス計算(100マス計算)です。 ・計算力 ・集中力 ・姿勢 ・返事…声を出す ・手を挙げる などなど、1つの活動の中でいろいろな力を伸ばすことができます。 私の学級では、一石十鳥くらいでしょうか。 私の場合、「学習能力」という視点で見ています。 |
| 音 音をなくす、無駄な音を少なくする… 音に着眼すると、飛躍的に成長します。 1日、学級の音に注目してください。 いかに音が大きいか。 無造作に音を出しているか… ・椅子をひく音。 ・足音。 ・授業中の私語。 などなど。 感性の問題ですね。 |
| スピード すごい学級は、スピードがあります。 動きの1つひとつ、切り替え、かたづけなどなど。 すべてにおいて、速いです。 圧倒的な差があります。 ・さっと取りかかる。 ・次の活動へのつなぎ(終わり→次の活動のはじめ) |
| さりげなさ |
時間 時間に着目します。 たとえば、1単位の授業時間です。 小学校の場合、たいてい45分ですね。 どうして、45分なのでしょう。 どうして、1年生も6年生も同じ時間なのでしょう。 何かを書かせる場合、何分が適当でしょうか。 最近開発しているのが、ショートタイムの授業です。 1分間の授業、3分間の授業、5分間の授業 ちょっとした時間を活用しています。 ・『いろはかるた』の超高速読み 1分 ・歌の練習 1〜3分 ・合唱構成『ぞうれっしゃがやってきた』台詞だけ 5分 |
片づけ方 給食片づけ。 どうせ捨てるんだから… ぐちゃぐちゃに詰めても、きちんとやっても変わらないという考えがあります。 「お金を払っているのだから」という意識に通じますね。 私の場合、このように考えません。 捨てるものであろうと、大事にしたいと思っています。 飲み屋さんにいっても、ファミレスにいっても、きれいに片づけます。 給食の場合も、同様です。  みかんの皮は、左のようにして返します。 みかんの皮は、左のようにして返します。給食主事さんには好評です。 |
漢字るび 低学年を受け持つと、必ずやるのが漢字るび。 国語の教科書ひらがな部分を、漢字になおさせるのである。 漢字のるびを振らせるのである。 たとえば、「かえる」は「蛙」というように。 おもしろですよ。 子どもたちは、この漢字るびが大好きです。 |